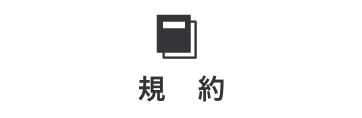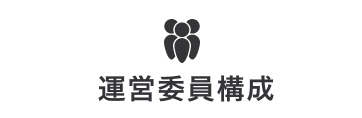投稿記事
ぶんせき誌への活動紹介の投稿記事
第394回ガスクロマトグラフィー研究会・見学会 開催報告
実施日:2026年1月29日
実施場所:日本生活協同組合連合会 商品検査センター
今年は埼玉県戸田にある生活協同組合連合会 商品検査センター(日生連)で見学会を行った。見学会当日である1月29日は快晴でよく晴れたものの,空気が冷たい1日であった。
北は北海道,南は福岡県と日本全国から30名が参加,運営委員も含め総勢 35人の見学会となった。見学会に先立ち,日生連から商品検査センターの役割,作物残留農薬分析,異臭分析の紹介があった。「健康被害や危険物の混入・異味異臭などは現品を確認し,取引先への即時調査依頼,必要な検査と工場点検の実施を判断する」ということで,生協ならではの会員ファーストの検査体制が印象的であった。作物残留農薬分析では生協標準検査法を作っており,GC-MS/MSやLC-MS/MSを駆使して,2024年度実績で1000検体以上を測定していた。質疑応答でも検査体制や基準値管理の方法など活発なやり取りが交わされていた。異臭分析では,商品検査センターの特徴として嗅覚官能検査で異臭を確認したのち,におい嗅ぎGC/MS分析を実施している。におい嗅ぎに使うGC/MSは1D/2Dシステムが導入され,ハートカットといってニオイが溶出する部分を別のカラムに導入し,より純度の高い測定を行うことで,ニオイを判定していた。このような異臭分析は迅速な対応と様々な経験や知識が必要とされることに改めて驚かされた。
日生連のご講演に続き,株式会社エスコの坂先生による「残留農薬分析の国内外における現状」というタイトルでご講演をいただいた。国内外で提唱されている分析方法を比較されており,原理や注意点などについても触れられていた。
最後の見学では3グループに分けられ,検査センターを見学した。検査センターでは現在50名ほどが勤務されており,講演で紹介された作物残留農薬,異臭分析のもほかにも,アレルゲンの検査や放射能測定なども実施されていた。多くの参加者が驚いたのはアレルゲン検査や作物残留農薬分析で最も気を使うコンタミ防止のために,標準溶液等の調整室,前処理室,測定室が分けられていることであった。多少検査は縮小しているとのことであったが,空いた検査室を有効に活用していた。全体として,一人一人が責任を持つと同時に強いチームワークで迅速,正確な測定を実施していることが,日生連の強みであると感じた。
(麻布大学 杉田和俊)


第393回ガスクロマトグラフィー研究会・講演会 開催報告
2025年11月26日(水)に北とぴあペガサスホールにて第393回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会が実施された.第393回のGC懇研究会では「匂い・香り分析」をテーマに主題講演3件および技術講演6件を実施した.幹事は羽田委員(玄川リサーチ)に依頼し,プログラムを組んでいただいた.参加者数は90名以上と盛況であり,臭いや香りの分析に興味を持つ研究者が多いことを実感した.プログラムは以下の通りである.
主題講演(1) 「超臨界流体クロマトグラフィーによる揮発性化合物の分析と結晶スポンジ法による同定」 (キリンホールディングス)谷口 慈将
主題講演(2) 「GCー熱分解ーGC-燃焼ーIRMSによる香気成分の部位別同位体分析:バニリンの起源追跡への応用」 (東京科学大学)山田 桂太
技術講演(1) 「においに関するガスクロの利用と試験のご紹介」 (環境管理センター におい・かおりLab)森 孝之
技術講演(2) 「GCxGC-TOFMSと機械学習を用いた構造解析手法のスパイス香気成分分析への適用」 (日本電子)窪田 梓
技術講演(3) 「オンラインSPE-GC/MSシステムによる固相脱水誘導体化法を用いた香気成分自動分析」 (アイスティサイエンス)松尾 俊介
技術講演(4) 「皮膚ガス採集方法と測定、及び皮膚ガス一酸化窒素の測定」 (ピコデバイス)津田 孝雄
技術講演(5) 「Solvent Assisted SBSE (SA-SBSE) と発酵食品の香気分析への応用」 (ゲステル)笹本 喜久男
技術講演(6) 「ユリ花から抽出したアロマウォータの香気成分解析」 (MCエバテック)西山 真由美
主題講演(3) 「臭気分析とGC-MSの使用法」 (ワイ・エム・ピー・インターナショナル)加藤 寛之
主題講演(1)では,ビールの苦み成分などの有機化合物をHPLCやSFCで単離後に結晶スポンジに取り込み,X線回折法により構造決定する手法について紹介があった.特にSFCは移動相の除去が容易であり結晶スポンジ法との相性が良く,単体では結晶を得ることが難しい様々な有機化合物の立体構造解析に有用であることが示され,その有用性や将来性を知ることができた.
主題講演(2)では,13Cと12Cの同位体比を用いる同位体質量分析法(IRMS)と熱分解を組み合わせる方法を用いて有機化合物の由来を調べる技術について紹介があった.講演ではバニリンを例にIRMSの有用性,現状や今後の展望などについて紹介があり,MSの応用性や可能性をさらに深く知る事ができた.
主題講演(3)では,GCを用いる臭気分析に関して,長年の経験を元に失敗や成功を含む多くの事例の照会があった.異臭のクレームがあった際の官能評価の重要性や異臭原因物質のピークが小さく,クロマトグラム上で見づらい場合の前処理の重要性など,経験に裏打ちされた貴重な講演を聞くことができた.
技術講演では臭い分析の受託試験の例の紹介,機械学習を用いたGC×GC-TOFMSによる未知化合物の構造決定法の紹介,オンラインSPE-GC分析による香気成分や短鎖脂肪酸などの分析技術の紹介,皮膚ガス分析の意義や分析例および今後の展望についての紹介,溶媒膨潤を利用するスターバー抽出法による香気成分の分析の紹介,ユリの花を水蒸気蒸留法により抽出した際の香気成分の分析結果の紹介があった.
「匂い・香り分析」と言っても,様々なアプローチがあり,それらの知見が融合されてより良い分析技術が構築されていくことを改めて実感した.
講演会終了後は会場を移して約30名で意見交換を行った.講演者への質問の他にもGC関連企業やユーザー間で活発な意見交換が行われた.
(山梨大学 植田 郁生)
第392回ガスクロマトグラフィー研究会・講演会 開催報告
2025年9月24日(水)に日本分析化学会第74年会(北海道大学)において第392回GC研究会・講演会が実施された。今回のGC懇講演会では元旭川医科大学の阿久津弘明先生にご講演をいただいた。阿久津先生は質量分析学会で精力的に活動されており、「SPME/GC/MSを用いた森林大気の分析 -森林ウォーキングの効用-」と題したご講演を行っていただいた。高齢者が森林ウォーキングを行うことで、血圧の低下、認知機能の改善などが見られた。その際にSPMEとGC/MSを用いて森林大気中のと高齢者の血液中からテルペン類を検出した。ウォーキングのみでも改善効果は見られるものの、森林ウォーキングの方がより改善効果が大きい傾向が見られており、森林中のテルペン類の香りを嗅ぐこと自体あるいは血中に取り込まれることにより何らかの良い影響が見られるというご講演であった。北海道の森林をウォーキングした研究成果であり、北海道での講演会に相応しいご講演であった。また、誰もが高齢者を迎えるため、全員が当事者であるため非常に興味深い内容であった。講演会場の教室はやや小さい会場であり、聴講者は50名以上で座りきれないほどであった。
阿久津先生のご講演の後はGC懇運営委員の瀬戸氏(理化学研究所)のご発表および渡辺氏(フロンティア・ラボ)のグループのGC関連の発表がそれぞれあった。また、引き続いてGC関連の講演として技術功績賞を受賞した辻󠄀田氏(福岡県警)の講演があった。いずれも会場は多くの聴講者が集まり、立ち見が出るほどの盛況振りであった。
(山梨大学 植田郁生)
第391回ガスクロマトグラフィー研究会 開催報告
2025年6月27日(金)に北とぴあペガサスホール(東京都北区)にて第391回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会が実施された。例年ガスクロマトグラフィー研究懇談会の6月講演会はGCの基礎的な内容を学ぶ機会としており、今年はGCの基礎の講義のほか、GCを上手に使うためのコツや使用上の注意点、トラブルシューテイング等の内容を含めた、実践的な内容の講演会を開催した。参加者数は74名であり、比較的若い人の聴講が多かったように見受けられた。会場では無料の資料展示を行っており,GCに関連する最新の製品や技術に関する活発な意見交換が行われた。当日のプログラムは以下の通りである。
第391回GC研究懇談会
2025年6月27日(金)13:00〜17:40
開会挨拶 杉田 和俊(GC研究懇談会委員長)
【基礎講座】
1.「GC,GC/MSの導入方法概説と上手な使い方」(山梨大学)植田 郁生
2.「キャピラリーカラムの基礎と上手な使い方」(Restek)千葉 拓也
3.「GC検出器の基礎と上手な使い方」(西川計測)山上 仰
4.「GC/MSの基礎と上手な使い方」(アジレント・テクノロジー)中村 貞夫
【技術講演】
1.「SPMEの基礎と上手な使い方(仮)」 (シグマアルドリッチ) 植田 泰輔
2.「HSとP&Tの基礎と実践」 (GLサイエンス)石井 一行
3.「サンプリングバッグの使い方」 (近江オドエアーサービス)安陪 智史
4.「Brevis GC-2050の最新のユーザー支援技術の紹介」 (島津製作所)内山 新士
5.「高分解能MSの紹介と電場型フーリエ変換GC/MSの基礎」 (サーモフィッシャーサイエンティフィック)秦 一博
閉会挨拶 杉田 和俊(GC研究懇談会委員長)
意見交換会(プロント王子店)
基礎講座1題目では山梨大学植田様より、試料注入法の基礎的な話を中心に、試料調整方法などの初心者が注意したいポイントを含めて講演いただいた。2題目のRestek千葉様からは、カラムの基礎的な原理から、カラムの各種パラメータが変わった際の分離パターンの違い等を講演いただいた。3題目の西川計測山上様より、GC検出器の特徴や基礎的な使い方、検出下限などについて講演いただいた。4題目のアジレント・テクノロジーの中村様より、GCMSの原理から、GCとの分岐や各種データベースの紹介等があり、いずれの講演も初心者に有益な講座であった。
次に技術講演では前処理等を中心に各メーカから多岐にわたるトピックが紹介された。いずれも基礎的な原理を含む内容から応用まで含まれており、大変興味深い内容であった。講演会終了後は30名超で意見交換会を行い、親睦を深めつつ有意義な情報交換がなされた。
(株)島津製作所 内山 新士

第390回ガスクロマトグラフィー研究会講演会・見学会 開催報告
第390回研究会として、3月21日金曜日に麻布大学「いのちの博物館」の見学会と麻布大学の先生による講演会を行なった。当日は、桜はちらほらといった感じであったが、とても暖かく春らしい1日であった。麻布大学「いのちの博物館」は創立125周年事業の一環として設立され、実際の動物の骨格標本を中心に展示されており、犬がペットとして飼われるようになり、骨格が丸みを帯びるように変化した過程や一部ではあるものの実際の象や鹿の骨格標本に触って重さや大きさを感じることができる貴重な体験であった。
また、講演会では麻布獣医学部獣医学科 栄養学研究室の鈴木武人先生と生命・環境学部臨床検査技術学科 生化学研究室の曽川一幸先生に日頃の研究成果を紹介していただいた。鈴木先生からは「ウシの第一胃発酵産物よもやま話」ということで脂肪酸の働きが非常に重要であり、揮発性脂肪酸が牛にとって重要な栄養源であること、体内時計に影響することなど、非常に興味深い講演であった。曽川先生からは「質量分析計を用いた細菌同定・疾患マーカー探索」ということでTOF-MSやOrbitrap MSを使って飲酒マーカーや16S rRNA methodによる細菌類の同定について講演され、細菌同定の技能試験における苦労話を楽しくお話しいただいた。参加者は10名と少し少なめであったが、講演後の質疑応答でも活発な意見交換が行われ、2時間の講演時間はあっという間に過ぎてしまった。意見交換会は曽川先生も参加され、焼肉を突きながら大いに盛り上がった。筆者は次の日、麻布大学で研究を兼ねたイベントに参加するため、帰途についたが、曽川先生ほか数名は更なる親睦を深めたようである。
麻布大学 杉田 和俊

第389回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会 開催報告
2025年2月7日(金)に北とぴあペガサスホール(東京都北区)にて第389回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会が実施された.2024年度はガスクロマトグラフィー(GC)生誕70周年を記念して表彰を実施しており,386回,388回に続いて受賞講演を2件実施した.また,「標準物質(ガス)の値付けに貢献するガスクロマトグラフィー」と題して4件の主題講演および5件の技術講演を実施した.参加者数は約45名であり,講演内容は後日参加者に配信予定である.さらに,GC懇の研究会では休憩中に会場で無料の資料展示を行っており,GCに関連する最新の製品や技術に関する活発な意見交換が行われた.当日は午前中にGC懇の運営委員会を実施した.午後からの研究会のプログラムは以下の通りである.
第389回GC研究懇談会
2025年2月7日(金)13:00〜17:50
開会挨拶 佐藤 博(GC研究懇談会 委員長)
【奨励賞受賞講演】
1. 「熱分解GC/MSによる異物分析に関する研究とその利用」
木下 健司((地独)東京都立産業技術研究センター)
2. 「低圧GC/MSの利用に関する研究」
大塚 克弘(ムラタ計測器サービス)
【主題講演】
1. 「JCSS標準物質のトレーサビリティと国際整合性」
渡邉 卓朗(産総研)
2. 「GCでも利用可能で国家標準にトレーサブルなJCSS標準ガス」
勝又 啓一(製品評価技術基盤機構認定センター)
3. 「JCSS制度における濃度信頼性試験」
東 純治(化評研)
4. 「自動車排ガスの濃度測定に使用されるNO+NO2混合標準ガスの評価」
園部 淳(エア・リキード・ラボラトリーズ)
【技術講演】
1. 「ポストカラム反応GCを用いた有機混合標準ガスの濃度値付け範囲の簡易な拡張方法」
佐々木 智啓(堀場エステック)
2. 「ガス混合装置の構造について」
乗矢 隆良(コフロック)
3. 「PLOTカラムの基本を学び、実践で活用する方法」
千葉 拓也(レステック)
4. 「水試料の測定に適した高極性のイオン液体カラム-Watercolカラム」
植田 泰輔(メルク)
5. 「Smart Aroma Databaseの紹介」
内山 新士(島津製作所)
閉会挨拶 佐藤 博(GC研究懇談会 委員長)
18:00〜20:00 意見交換会(プロント王子店)
まず木下氏の受賞講演では,赤外分光分析だけでは困難であった異物分析を熱分解GC/MSを使用することで解決した例などについて紹介があった.大塚氏の受賞講演では,GC-MS分析において主カラムの前方にナローボアのキャピラリーカラムを取り付けてカラム内を減圧することにより,分離度が向上する例やその際に窒素をキャリアガスに用いて分析する例について紹介があった.
次に主題講演では渡邊氏から,SIトレーサブルな標準ガスの供給体系とJCSS(計量計測トレーサビリティの確保のための制度と校正事業者登録制度からなる制度)と一般混合ガスの違いが明瞭に説明され,ガスクロが標準ガスの濃度値付けに貢献していることが説明された.勝又氏から,JCSSの紹介,トレーサビリティの説明,および校正事業者登録制度を説明された.またMRAと呼ばれる多国間の相互承認制度によって外国でも日本の標準ガスが使用できるという便利な制度が説明された.東氏から,標準ガスにおける濃度信頼性試験の重要性,およびガスクロを使用した14種類VOC混合ガスの一斉分析方法が提示された.主題講演の最後に園部から,自動車排ガスの濃度測定に使用されるNOとNO2の混合標準ガスをシリンダー中で安定化するため,シリンダー内面処理,あるいは温度や圧力の影響について詳細に試験した結果が示された.実試料中のガス濃度を精度よく決定するために,信頼性が高い標準ガスを使用することが必要であり,国家標準にトレーサブルな標準物質の作成段階からユーザーに渡るまでの工程や品質が高い標準ガスを届けるために公的研究機関,あるいはガス製造会社から日々の活動などについて様々面からの貴重な講演を聞くことができた.技術講演では,ポストカラムを用いた最新の定量分析技術,ガス混合装置を使用して濃度を可変する技術,PLOTカラムの基礎や使用上の注意点,最新のキャピラリーカラム固定相,最新のデータベースを用いた定性技術について紹介があった.講演会終了後は20数名で意見交換会を行い,時間の関係で講演では話すことができなかった情報を交換し,ガスクロの技術向上を行うための有意義な時間を過ごした.
(株)エア・リキード・ラボラトリーズ 園部 淳

第388回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会 開催報告
2024年11月27日(水)に北とぴあペガサスホール(東京都北区)にて第388回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会が実施された.今年はガスクロマトグラフィー(GC)生誕70周年を記念して表彰を実施し,386回に続いて受賞講演を実施した.また,「持続可能な社会に貢献するガスクロマトグラフィー」と題して国立研究開発法人国立環境研究所の中島大介先生と元麻布大学生命環境学部教授(現麻布大学発ベンチャー 株式会社食機能探索研究所BABILON代表)守口 徹先生にご講演を頂いた.さらに5件の技術講演を行なった.参加者数は約60名であり,講演内容は参加登録者に後日動画配信予定である.GC懇の講演会では会場においてGCに関連する企業が無料で資料の展示を行なっており,休憩時間中に最新技術の紹介などの活発な意見交換が行われた.当日のプログラムは以下の通りである.
第388回GC研究懇談会講演会
2024年11月27日(水) 10:00〜17:40
開会挨拶 佐藤 博(GC研究懇談会 委員長)
【受賞講演】
1. 「GC/TOFMSと機械学習を用いた未知化合物の構造決定に関する研究」
生方 正章(日本電子(株))
2. 「ボールSAW検出器の実用化と小型GCの開発研究」
赤尾 慎吾(ボールウエーブ(株))
3. 「特殊ガス・純ガスの高度化に関連する技術開発と利用に関する研究」
園部 淳((株)エア・リキードラボラトリーズ)
4. 「ビールの香りを構成する香気成分群に関する研究」
岸本 徹((元)(独)酒類総合研究所)
【技術講演】
1. 「オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)による河川水中農薬の簡便・迅速な分析法の検討」
鈴木 健司((株)アイスティサイエンス)
2. 「Jetanizer及びPolyarcの製品紹介」
内山 新士((株)島津製作所)
3. 「GC-MSのヘリウム供給問題を解決!ヘリウムセーバーと各サンプリング法(液打ち・HS・SPME・PT・熱分解など)の実用例」
秦 一博(サーモフィシャーサイエンティフィック(株))
4. 「未来のラボを支える最小の高性能ベンチトップ新型GC」
風間 春奈(アジレント・テクノロジー(株))
5. 「GC/MS検量線データベース法(AIQS-GC)に対する弊社の取り組み」
山上 仰(西川計測(株))
【主題講演】
1. 「平時調査につなげる事故・災害時の化学物質スクリーニング技術」
中島 大介(国立環境研究所)
2. 「食生活におけるオメガ3系脂肪酸の重要性−脂肪酸分析が教えてくれたもの−」
守口 徹(食機能探索研究所BABILON 代表,((元)麻布大学)
閉会挨拶 佐藤 博(GC研究懇談会 委員長)
18:00〜 意見交換会(北とぴあ17階レストラン QUAD17)
まず受賞講演では,GCに関する新規技術の開発やGCを用いた最新の研究成果について講演していただいた.研究中に遭遇する様々な問題点について,どの様に解決して受賞に至る成果を挙げてきたのか各受賞者から聞くことができた.次にGCに関する新しい技術の紹介を含む技術講演を実施した.GCは比較的成熟した分析技術ではあるが,GC装置,データ処理および試料前処理においてまだまだ新技術が紹介されており,GCも進歩していることを実感した.最後に主題講演を行っていただいた.中島先生(国立環境研究所)からは,災害時における化学物質の漏洩問題に関する環境モニタリング体制の現状や今後の課題,モニタリング体制の構築の重要性などについて講演をいただいた.災害時には行政が主体となって化学物質の漏洩をモニタリングすることが必要となり,その難しさや課題については多くの聴講者が初めて聞く内容であり,貴重であった.守口先生(元麻布大学)からは日頃の食事においてオメガ3系脂肪酸を接種することの重要性について,最新の研究成果を交えて講演していただいた.オメガ3系脂肪酸欠乏飼料で飼育したマウスの行動観察から判明したオメガ3系脂肪酸の欠乏が我々の生活に与えうる影響は,全人類にとって重要であり,聴講者の今後の生活に影響し得る大変興味深い内容であった.
講演会終了後は会場を移して約40名で意見交換を実施した.当日の講演者への質問や意見交換を中心に,GC関連企業やユーザー,研究者間で活発な意見交換が行われた.
山梨大学 植田 郁生

第386回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会・表彰式 開催報告
2024年6月28日(金)に北とぴあペガサスホール(東京都北区)にて第386回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会が実施された.今年はガスクロマトグラフィー(GC)生誕70周年を記念して表彰を実施した.午前に下記9名の方にGC懇委員長より表彰状の授与および記念撮影が行われた.
【奨励賞】
木下 健司 ((地独)東京都産業技術研究センター
生方 正章 (日本電子(株))
松尾 俊介 (アイスティサイエンス)
大塚 克弘 (ムラタ計測器サービス)
【技術功績賞】
赤尾 慎吾 (ボールウェーブ)
渡辺 壱 (フロンティア・ラボ)
園部 淳 (エア・リキード)
【研究功績賞】
岸本 徹 (元(独法)種類総合研究所(現 日本たばこ産業))
稲葉 洋平 (国立保健医療科学院)
午後からはGC懇講演会を実施した.本研究懇談会では例年,新年度最初の講演会では基礎的な内容を主体とした講演会を実施しており,今回は講演主題を「GC,GC/MSの基礎を学ぶ」として幅広くGCの基礎について講演会を行った.当日の参加者は約60名であった.発表内容は後日動画配信も行っており,数名が配信動画の視聴による参加であった.会場ではGCに関連する企業が無料で資料の展示を行い,休憩時間中に最新技術の紹介などの活発な意見交換が行われた.当日のプログラムは以下の通りである.
第386回GC研究懇談会講演会 13:00〜17:50
開会あいさつ 佐藤 博(GC懇委員長)
【受賞講演】
1. 「GCの大量注入法及び固相抽出技術の自動化やオンライン化に関する技術の普及」
松尾 俊介(アイスティサイエンス)
2. 「GC/MS/MSを用いたたばこ煙中の多環芳香族炭化水素に関する研究・開発」
稲葉 洋平(保健医療科学院)
3. 「熱分解GC/MSを用いたマイクロプラスチック分析システムの開発と製品化」
渡辺 壱(フロンティア・ラボ)
【主題講演】
「GC,GC/MSの試料前処理・導入方法概説」
植田 郁生(山梨大学)
【技術講演】
1. 「キャピラリーカラムの基礎と選択方法」
海老原 卓也(Restek)
2. 「ヘッドスペース分析の基礎と使い方」
内山 新士(島津製作所)
3. 「加熱脱着の基礎と使い方」
森 拓也(ゲステル)
4. 「質量分析計の基礎と使い方」
風間 春奈(アジレント・テクノロジー)
5. 「キャニスター採取の基礎」
小野 由紀子(西川計測)
閉会のあいさつ 佐藤 博(GC懇委員長)
意見交換会(会場)
まず受賞者の内3名の方に受賞講演を行っていただいた.受賞に至ったGCに関連する新規分析技術の開発やGCを使った最新の研究成果について講演していただいた.11月に実施予定の講演会においても,引き続き受賞講演を実施予定である.次に筆者がGCの試料導入に関する基礎について講演を行った.GCには試料注入に関して多くのノウハウや注意点があるため,気体試料と液体試料の両方を注入する際のそれぞれの注意点などについて講演した.その後,5件の技術講演を実施した.プログラム委員からの依頼により,カラム,試料前処理,検出器とGCに関連する幅広い分野について,関連する企業の方々に基礎から最新技術まで幅広く講演していただいた.
講演会終了後は15分程度であったが会場で引き続き意見交換会を行い,その後に場所を移して約30名で意見交換会を実施した.初めてGC懇の研究会に参加した方々からは,大変勉強になったとの声も頂戴し,基礎を学ぶ今回の研究会の趣旨がGCユーザーの役に立っていると実感することができた.
山梨大学 植田 郁生


第385回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会 開催報告
2023年11月30日(木)北とぴあ飛鳥ホール(東京都北区)において、第385回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会が開催された。本研究懇談会では毎年年末の近くなった時期に特別講演会を開催しており、今年度は「工業製品の発展と共に活躍するガスクロマトグラフィー−関連材料の管理や調査におけるGCの役割と展望−」というテーマのもと、この分野で活躍する講師による5題の主題講演のほか、メーカー各社による5題の技術講演からプログラムが構成された。現地では80名を超える参加者が集い、10時開始から17時を超えるまでと長丁場であったものの、聴衆から高い関心が寄せられていた。
冒頭の2題の主題講演では食品包装に関連したテーマが並び、カデラ薬品金子様(前・東京都健康安全研究センター)による「食品用器具・容器包装の試験検査について」では、GC以外の範囲を含め数多くの具体例を挙げながら規格に基づいた試験方法が示され、イメージしやすく実際的な進め方の紹介がなされた。化学研究評価機構 食品接触材料安全センター梶原様による「食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度について」では、関連法の動向やポジティブリスト制度施行後の実際的な状況が示され、事業者と連携しつつ見直しをはかりながら進められていることを窺い知ることができた。
日産アーク沼田様による「臭気分析におけるGC-MSと多変量解析の活用」では、臭気分析の基本的な考え方から評価方法までの全体像や材料由来の異臭測定の具体例が提示されたほか、多変量解析を適用した取り組みについて紹介がなされ、多変量解析の臭気成分の要因調査への有用性が認識された。
講演会最後の2題ではブラスチック材料の使用後の挙動に関連して、マイクロプラスチックやケミカルリサイクルについての講演が続いた。徳島大学水口様による「熱分解GC/MSによる大気マイクロプラスチックの分析」では、本分野における分析手法として熱分解GC/MSの有用性、実際的な分析条件の検討や測定例が紹介されたほか、サンプリングにおける微小サイズゆえの難しさやより一層の注意深さの必要性が認識された。また、研究分野として今後ナノサイズへ移行していくとの予測が示された。東北大学熊谷様による「プラスチックのケミカルリサイクルプロセス開発への熱分解ガスクロマトグラフィーの応用」では、プラスチックリサイクルの背景や今後の見通しとしてリサイクル対象が増えていく展望に加え、熱分解反応を利用したケミカルリサイクルプロセスとして、PETからベンゼン、ポリカーボネートからビスフェノールAやフェノール、ポリウレタンからイソシアネートの回収といった開発事例が紹介された。熱分解反応機構は複雑であり、反応解析には熱分解GC/MSによる分析的なアプローチが適用されていた。
その他に技術講演においては、アジレントテクノロジー 風間様による「食品用器具・容器包装添加剤分析用データベースの紹介」、日本分析工業 大栗様による「工業製品分析のための加熱脱着装置の開発」、島津製作所 内山様による「GC/MS異臭分析システムの紹介」、日本電子 生方様による「GC-TOFMS専用自動構造解析ソフトウェアを用いた製品中異物の差異分析・構造解析」、フロンティア・ラボ 松枝様による「窒素キャリヤーを用いるGCと熱分解GC/MSの基礎検討」という多岐にわたるトピックが紹介された。その他に、講演の合間には14団体から資料提供頂き、スペースを設け、会場での意見交換も行われた。なお、当日の講演は後日参加登録者へ向け録画配信がなされる。
以上のようにガスクロマトグラフィーが様々な形で実社会へ関与、貢献していることを改めて認識することができる講演会であった。また、講演会後には数年ぶりに講演者を含めた意見交換会・懇親会が行われ、親睦を深めつつ有意義な情報交換がなされた。最後に、本講演会の開催にあたり、ご講演をご快諾していただきました講師の皆様、ご来場いただきました皆様に心より御礼を申し上げます。
〔(地独)東京都立産業技術研究センター〕 木下健司
第383回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会・見学会 開催報告
第383回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会・見学会は、2023年8月25日(金)、国立研究開発法人理化学研究所放射光科学研究センターの「SPring-8/SACLA」(兵庫県佐用郡佐用町)にて開催いたしました。分析化学分野においても活用されている放射光技術に関して、SPring-8/SACLAの現状と可能性を御紹介頂きました。SPring-8は1997年に運転を開始した周長1436メートルの施設で世界最大のエネルギーを持つ放射光発生装置でその名前はSuper Photon ring-8 GeV(80億電子ボルト)に由来します。SPring-8内では47本の放射光が出され、それらの放射光を使って実験できる場所(ビームライン)が58カ所あり、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、産業利用まで多様な研究が進められています。
当日は13:00より施設内のSACLAホールにて、講演会を開催いたしました。講演会と見学会には24名が参加いたしました。講演会では、まずGC研究懇談会の佐藤委員長からの挨拶の後、今回の講演会と見学会の開催に全面的に御協力を頂きました、理化学研究所 放射光科学研究センター 法科学研究グループリーダーの 瀬戸康雄先生より「SPring-8と理研RSC法科学研究グループの研究開発」について御講演を頂きました。SPring-8の沿革や法科学研究グループにて瀬戸先生がリーダを務められているグループでの研究事例を踏まえ、日本の法科学を支える微細分析の研究を御紹介いただきました。続いて理化学研究所 放射光科学研究センター SACLAビームライン基盤グループの菅原道泰先生より「SACLAと構造生物学」について御講演を頂きました。菅原先生がこれまで取り組まれてきましたX線解析装置への結晶の注入方法の開発を中心とした結晶構造解析の最先端の取り組みについて御紹介を頂きました。そして、私、岸本徹(酒類総合研究所)より「ビールの香りに寄与するチオール化合物の新規前駆体型の発見」という内容について発表をさせて頂きました。ここでは新たに発見した前駆体である「ジスルフィド結合型の低分子チオール」について報告をさせて頂きました。
15:30より見学会として、まず全長700mのSACLAを見学いたしました。SACLAは、原子や分子の瞬間的な動きをストロボ写真のように観察することができるX線のレーザーで、2021年からは、波長1以下の世界最高性能の光を生み出すSACLAの加速器から、高品質な電子ビームをSPring-8に入射しています。ここでは壮大な加速器棟、電子からX線レーザーを生成するアンジュレーターを見学いたしました。精密な装置をこれほどにまで長距離に渡って精緻に並べて、強力なX線レーザーを生成する設備とそれを完成させた技術に圧倒されました。続いて、SPring-8内のビームラインを用いた実験設備を見学いたしました。分光分析を行うBL(ビームライン)37XUでは、瀬戸先生らのグループが毛髪中の元素を検出されている事例を御紹介いただきました。マイクロCTとして使用されているBL47XUでは、はやぶさ2サンプルのX線CTを用いた分析、放射光ナノCTによる小惑星リュウグウ微細粒子の内部構造解析の研究を紹介いただき、このSPring-8が世界の研究をリードしていることを実感いたしました。その後、物理棟3階の法科学研究グループを見学いたしました。こちらでは、レーザーラマン分光光度計、ICP発光分光分析装置、偏光傾向顕微鏡、GC-TOF装置など日本の警察捜査を支える最先端設備を紹介いただきました。
その後、18:00からの懇親会には17名が参加し、さらにそのうち14名がSPring-8内にあるゲストハウスに宿泊いたしました。深夜までお酒を交わし、交流を深めることができました。 今回の見学会を通じ、日本が国力を掲げて完成させた壮大な研究施設に感銘を受けると共に、それらを完成させ、研究を支えているのは高いレベルの日本の人材であると改めて感じました。精緻な世界最高の研究施設から今後発表される、多くの研究結果は世界をリードして行くと確信いたしました。
(酒類総合研究所) 岸本 徹

SPring-8 SACLA見学会の集合写真
第382回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会
2023年6月23日(金)に北とぴあペガサスホール(東京都北区)にて第382回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会が実施された.本研究懇談会は例年,新年度の最初の講演会では基礎的な内容を主体とした講演会を実施しており,今回は「試料前処理と試料導入」に関する基礎と最新技術について講演会を行った.講演会は対面形式で開催し,当日の発表内容は後日動画配信も行った.当日に会場で聴講した参加者は約70名であり,多くの参加登録者が会場に足を運んだようである.会場ではGCに関連する企業が資料の展示を行い,休憩時間に活発な意見交換が行われた.当日のプラグラムは以下の通りである.
第382回GC懇講演会プログラム13:00〜17:00
開会あいさつ (GC懇委員長・長崎国際大)佐藤 博
【基礎講座】
「試料前処理の基礎」
(麻生大学)杉田 和俊
まず,今回のテーマである試料前処理について,その目的や重要性,手法等について,基礎から講演をしていただいた.GCで複雑な試料や希薄な試料を正確に定性・定量するためには,適切な試料前処理が必要であり,目的や試料の状態に応じて様々な手法が選択可能であることや、基本的な試料前処理法の原理や注意点などが紹介された.
【招待講演】
「阿蘇草地高原大気の観測からBVOCsのオゾン生成ポテンシャルを探る: TD-GC-CMFID/MS,化学発光検出,マイクロガス分析システム,SIFT-MSの活用」
(熊本大学)戸田 敬
大気中の微量ガス状成分をその場で分析するための分析システムの開発やその利用,さらに生物由来の揮発性有機化合物であるBVOCが大気環境に与えている影響など,大気分析に関する幅広い研究成果についてご講演をいただいた.最新の研究成果に触れて勉強になったのは無論のこと,戸田先生の知的探求心や問題解決能力を知る機会にもなった.最後に,今年の9月に開催予定の日本分析化学会第72年会(熊本)についても案内があった.
【技術講演】
下記8件の技術講演を行っていただいた.固相抽出(SPE),固相マイクロ抽出(SPME),加熱脱着や熱分解など,幅広い試料前処理法について基礎から最新の動向まで幅広く講演していただいた.
- 「「GC分析分野におけるSPE(固相抽出)法の基礎と事例」
(GLサイエンス)高柳 学 - 「SPME(固相マイクロ抽出)の概要と新製品について」
(メルク・シグマアルドリッチ)佐々木 豊 - 「Agilent 7693Aオートサンプラが最高のサンプル前処理・注入パフォーマンスを提供」_
(アジレントテクノロジー)風間 春奈 - 「微量ポリマー分析を可能としたF-スプリットレス熱分解法」
(フロンティアラボ)太田 惇貴 - 「GERSTEL DHS(ダイナミックヘッドスペース)の特徴と食品香気分析への応用『マルチモードによる感度/網羅性の向上』」
(ゲステル)神田 広興 - 「Entech 7200A 自動濃縮装置による微量低沸点化合物の測定」
(西川計測)小野 由紀子 - 「低温濃縮装置の技術と皮膚ガス及び電池空間における微量ガス測定への応用」
(ピコデバイス)津田 孝雄 - 「固相誘導体化によるメタボローム分析の前処理とその自動化に関する最新情報」
(アイエスティサイエンス)松尾 俊介
閉会の挨拶 (GC懇委員長・長崎国際大)佐藤 博
山梨大学 植田郁生


第381回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会開催報告
2023年2月17日(金)に、標記講演会を開催しました。当初は対面形式での開催を模索していましたが、準備段階での1月中において、新型コロナウィルス第8波による感染者数および季節性インフルエンザによる感染者数がどちらも増加しており、同時流行への対策の観点からオンライン開催形式となりました。講演主題は「持続可能な社会に役立つガスクロマトグラフィー第3回」で、近年注目されているSDGsをテーマとした講演会をシリーズ化しており、実験室の効率よい運営、多彩なデータ処理機能やデータ処理ソフトウェアの理解と使い方を話題として取り上げられました。2013年から引き続き課題となっているヘリウムガスの供給に関連したガスクロマトグラフィー分野での取り組みなども交え、1件の招待講演と6件の主題講演にて広く話題提供されました。当日は、50名以上の方に講演会へ参加していただきました。
招待講演では、国立研究開発法人産業技術総合研究所の羽成修康様より「短鎖塩素化パラフィン分析におけるガスクロマトグラフ質量分析計の分解能差の影響」と題して講演をいただきました。塩素化パラフィン類の定量に係る国際規格がすでに制定されていますが、実際の定量操作にはさまざまな困難があるとのことです。共同分析の結果を例に用いて、質量分析計の分解能差で比較した結果が紹介されました。妨害物質の影響を排除するためには高分解能が必要といわれており、共同分析の結果もこのことを示していました。また、高分解能測定機器を使用すれば十分というわけではなく、分析結果は試料組成の影響も受けるので、高分解能測定機器分析法の妥当性確認も必要ということでした。
主題講演は、テーマが2つに大きく分けられ、合わせて6件の講演が行われました。主題講演の1テーマ目は「GC、GC/MS分析におけるデータ解析について」と題して、4題の講演が行われました。1題目は、日本電子株式会社の生方正章様より「GC-TOFMS及び機械学習を用いた構造解析手法の開発と応用」と題して講演いただきました。GC/MSでの定性分析において、データベース(ライブラリ)に非掲載の物質の構造解析には、多くの知見と経験、時間が必要です。同社はAIを活用してこの作業を自動化するためのシステムを開発し、このシステムを用いて材料中の未知物質の構造解析を迅速に行った例が示されました。
2題目は、株式会社島津製作所の中村元哉様より「最新のクロマトグラムの波形処理について」と題して講演いただきました。分析者の取り扱う解析データ数が増加、また解析対象ピーク数も増加することで、波形処理パラメータ変更時の管理コストが増加し、波形処理の自動化・簡素化が求められています。同社はAIを活用した波形処理アルゴリズムを開発し、熟練技術者の波形処理を再現いたしました。従来では波形処理・同定処理に113分を要していた作業時間が、このアルゴリズムを活用することで同定処理のみの32分に低減した例が示されました。
3題目は、アジレント・テクノロジー株式会社の風間春奈様より「快適なラボワークを支えるAgilent OpenLab CDS 2ソフトウェアのご提案」と題して講演いただきました。複数の分析機器の使用環境下では、分析機器毎にソフトウェアの操作性などが異なっています。このような環境下での、データ解析とレポーティングに要する時間の低減を実現する一つの解として、同社のソフトウェアが紹介されました。ユーザーインターフェースデザインを工夫するとともに、GCやLCからシングルMSまでの装置管理を可能とし、他社製分析機器の制御を可能とすることで、ソフトウェア操作法習得のハードル、習得に要する時間の低減を目指したとのことです。使用時においても、必要時に必要な情報のみを表示することで、ユーザーの負担軽減に貢献できるとのことです。
4題目は、西川計測株式会社の山上仰様より「マルチベンダーGC/MSデータ解析用ソフトウェアAXELのご紹介」と題して講演をいただきました。複数メーカーの装置運用時では、装置間の互換性、操作性の違いの問題があります。また、同一PC上でのデータ解析の場合には、動作安定性の問題もあります。このような問題を解決する一つの解として、同社のソフトウェアが紹介されました。AIA形式のデータを活用して、装置によらないデータ解析を実現しています。また、MSスペクトルの結果とRetention Indexを組み合わせたデータベース、文献値掲載のRetention Indexを収蔵したデータベースを提供しており、これを活用することで定性分析の確度を上げることが可能とのことです。
主題講演の2テーマ目は「ヘリウム供給問題への対策」と題して、2題の講演が行われました。1題目は、ムラタ計測器サービス株式会社の大塚克弘様より「窒素をキャリヤーガスとしたLPGC/MSとその応用」と題して講演をいただきました。常圧条件時における窒素キャリヤーガスでの最適線速度は、ヘリウムキャリヤーガスでのものの二分の一から三分の一程度です。低圧(真空)下では、最適線速度は常圧条件時の2倍から3倍となります。カラム入口側に抵抗管を付けたメガボアカラムでカラム出口を質量分析計に接続してそのメガボアカラム内を真空にし、これを活用することで、窒素をキャリヤーガスとした場合であっても適切な分離を行いつつ測定時間の短縮も実現できたとのことです。ヘリウムキャリヤーガスと比べると、質量分析計のイオン化が阻害され感度は落ちてしまうものの、メガボアカラムを用いるので試料導入量が増やせるとのことです。また、検量線の直線性やピーク形状は問題ないとのことです。なお、公定法でのGC/MS測定ではヘリウム以外のキャリヤーガスを認めていないので、それを認めていただけるよう活動を行っていくとのことです。
2題目は、ジーエルサイエンス株式会社の伊藤深雪様より「代替キャリヤーガス使用上のポイント、節ガス対策、分析への応用例」と題して講演いただきました。ガスクロマトグラフィーのキャリヤーガスとして使用されるヘリウムの代替ガスとして、主に窒素や水素を取り上げて、各ガス種の特徴を説明いただきました。そして、分析装置での代替ガスへの切り替え手順と、実際の測定操作に係る注意点を説明いただきました。代替キャリヤーガスが使用できない場合には、スプリットガスでのガス使用量の低減方法などについて紹介いただきました。合わせて、マイクロGCといったガス使用量が小さい測定装置の使用も提案いただきました。
今回は、多彩なデータ処理機能やデータ処理のソフトウェアの理解と使い方についての話題が提供されました。ガスクロマトグラフィーの世界にもAIが応用され、データ解析に係る省力化が進みつつあります。ソフトウェア技術の進歩に驚くとともに、ソフトウェアを正しく活用するための技術習得が、分析者に対する新たな課題になるものと感じております。合わせて、昨今のヘリウム供給不足に関連した発表もありましたので、ヘリウム供給問題に悩まれている参加者にとっては、参考になったのではないでしょうか。
最後に、講演会の開催運営にあたり、事務委託とオンライン開催を支えて頂いた一般財団法人大気環境総合センターの皆様に、この場を借りて感謝いたします。
(国立研究開発法人産業技術総合研究所 渡邉卓朗)
第380回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会 開催報告
2022年11月18日(金)に北とぴあの飛鳥ホールにおいて、標記講演会を現地とオンラインのハイブリット形式にて開催しました。講演主題は「持続可能な社会に役立つガスクロマトグラフィー第2回」で、エア・リキードの園部委員と産総研の渡邉委員が幹事を務め2013年から課題となっているヘリウムガスの供給に関連した話題とガスクロマトグラフィー分野での取り組みを中心に2件の主題講演、1演題の招待講演と10演題の技術講演が行われ多くの情報が提供されました。参加者は、現地58名、オンライン41名の合計99名と大盛況のうちに終了いたしました。また、今回初めての試みとして休憩時間と講演終了後に意見交換の時間を取り、過去に研究会で展示して頂いた約50社に連絡して企業からのカタログなどの配布場所を設け資料提供頂き、参加者間での意見交換が活発に行われました。オンラインでの参加者にも幕間を利用して情報提供しました。
主題講演1題目は、日本エア・リキード合同会社の水澤芽衣様より「ヘリウム供給の現状」と題してご講演をいただきました。近年のヘリウム供給の状況やコスト上昇に関する背景、そして、今後の供給の展望について、紹介いただきました。たくさんお金を払う所に優先的に供給される仕組みのため、どこまで負担増に耐えられるかという厳しい現実もあるようです。2題目は、株式会社ジェイ・サイエンス・ラボの川村祥太郎様より「熱伝導度検出器を用いた液体水素中のオルト/パラ水素の分析」と題してご講演をいただきました。水素には核スピン異性体の存在により、オルト水素とパラ水素が存在するため、液化水素の貯蔵や輸送時にはそれら水素の比率の分析が求められています。比率を分析する目的や概要に加えて、熱伝導度型検出器を用いた応用分析例について、紹介いただきました。
招待講演では、一般社団法人日本環境測定分析協会・一般社団法人日本環境化学会の松村徹様より「ヘリウム代替ガス研究委員会の目的と活動」と題してご講演をいただきました。ヘリウム供給不足の現状に対応した、環境計量に係る公定法を改正するための枠組み作りと、現在取り組まれてる内容について紹介いただきました。公定法改正の難しさ、枠組みを作る大切さ、そして参加機関にとっても有益な仕組み作りと、異なる分野での公定法改正でも非常に参考になるお話でした。
技術講演の1題目は、金陵電機株式会社の上田透様より「オーブン内の水素漏洩検知と遮断切り替え機能を兼ね備えたガスクロマトグラフ」と題して講演いただきました。近年ヘリウムの供給が逼迫しているため、代替キャリヤーガスとして水素が検討されています。水素を使用する際の安全・安心対策機能を備えたガスクロマトグラフシステムについて具体的な対策が示されました。2題目は、日本電子株式会社の生方正章様より「GC/MSからはじめるSDGs〜定量分析における生産性の向上と代替キャリヤーガスについて」と題してご講演をいただきました。窒素キャリヤーガスを使用した水質基準・環境基準項目の測定および水素キャリヤーガスを使用した食品中残留農薬の測定を事例にとりヘリウムから転換する事例が紹介されました。3題目は、ミッシェルジャパン株式会社の松木洋介様より「キャリヤーガスにアルゴンを使用した検出限界<50ppbを達成するコンパクトオンラインガスクロマトグラフ」と題してご講演をいただきました。プラズマ中での発光検出器を用いた高感度オンラインガスクロマトグラフと応用例についてご紹介いただきました。無機ガスが高感度で検出可能で、一台の検出器で4つの検出波長を同時測定する事ができ、分離が難しい成分の測定に適用可との事です。4題目は、株式会社堀場エステックの小坂明正様より「質量分析法とポストカラム反応GC-FID法を組み合わせた香気成分の同時定性・定量技術のご提案」と題してご講演をいただきました。MSで定性し、成分が確定しても標準物質が無いため定量できない成分について、ポストカラム反応GC-FID法で値付けし、なおかつトレーサビリティを確保する方法が1回の分析で可能となる、という内容でした。5題目は、大阪ガスリキッド株式会社の河内拓哉様より「ガスクロマトグラフ分析におけるガス精製器の役割について」と題してご講演をいただきました。ガス精製の原理や仕組みに加えて、キャリヤーガス中の不純物を取り除くインライン精製器について紹介いただきました。キャリヤーガスの純度がガスクロマトグラフ分析に及ぼす影響や、純度が悪いHeをゲッター材を用いた精製器で高純度にするなどの役立つ情報が提供されました。6題目は、NISSHAエフアイエス株式会社の森郁子様より「金属酸化物半導体センサーを搭載したポータブルGCによる金属中拡散性水素分析」と題してご講演をいただきました。水素に高感度な検出器を用いる事で、来る水素社会で起こりうる水素脆性破壊の解決に寄与する新たな手法が紹介されました。7題目は、株式会社島津製作所の中筋悠斗様より「最新GC機能を一挙公開!ラボの自動化/省力化」と題してご講演をいただきました。自動運転のメリットに加え、異常発生時に安全に装置を停止する機能など生産性向上に寄与するシステムが紹介されました。8題目は、ドレーゲルジャパン株式会社の福留健司様より「VOC検知用ポータブルガスクロのご紹介」と題してご講演をいただきました。PIDを検出器とした携帯形GCで、連続測定でVOCの総量を検出し、漏洩ヵ所や安全確保が必要な個所でガスクロマトグラフによる個別成分分析に切り替えて現場で結果を出す事の利便性が紹介されました。9題目は、アジレント・テクノロジー株式会社の加賀美智史様より「水素キャリヤーガスに特化したGC/MSイオン源と水素利用上の注意点」と題してご講演をいただきました。水素をキャリヤーガスとしたときに生じるMSのイオン源での反応を抑制するイオン源の紹介と、水素をキャリヤーガスとして使用する際の留意事項などが紹介されました。10題目は、大塚製薬株式会社の藤峰慶徳様より「ゴマ汚染の評価に至適:エチレンオキシド、2-クロロエタノールの標準物質ならびに内部標準(安定同位体標識化合物)」と題してご講演をいただきました。新たな食品汚染の規制対象になる物質を測定する為の標準物質提供開始の最新の話題でした。
今回は、昨今のヘリウム供給不足に関連した発表が中心であったため、ヘリウムガスの節約法や代替キャリヤーガスを探している参加者にとっては、実務に役立つ有意義な講演会であったと感じます。開催運営にあたり事務委託とオンラインでの講演を支えて頂いた(一財)大気環境総合センターの皆様にこの場借りて感謝いたします。
(フロンティア・ラボ株式会社)渡辺壱

会場風景
第379回ガスクロマトグラフィー研究懇談会 講演会・見学会開催報告
2022年10月28日(金),東京都立産業技術センター(以下,都産技研)において,標題の講演会・見学会が開催された.2019年以来,コロナ禍で延期となっていたが,この度,参加人数を約30名に限定して開催された.今回の会場となった都産技研の本部は,ゆりかもめテレコムセンター駅からすぐのところにあり,道路を挟んで隣にフジテレビ湾岸スタジオがある.見学会当日は爽やかな秋晴れで,都産技研の建物前ではテレビ撮影が行われ,参加者はそれを横目に見ながら,都産技研に集うこととなった.
GC懇委員長の佐藤先生(長崎国際大)の開会挨拶後,都産技研・計測分析技術グループ長 林 英男氏から都産技研について,ご紹介いただいた.都産技研は東京都が設立した公設試験研究機関ということで,中小企業の振興を図るため,企業から多くの技術相談や依頼試験などを受けているとのことであった.参加者から東京都以外の企業でも技術相談等が出来るのかとのご質問があり,都産技研では東京都以外の企業からも相談等を受けていること,また,その際の料金は企業の規模に応じて設定されているため,東京都以外の企業でも都内の企業と変わらない金額で利用できる旨,ご回答があった.
都産技研のご紹介の後,都産技研・計測分析技術グループ 木下 健司氏から「熱分解装置を応用したGCによる技術支援〜異物分析、成分調査、不具合調査〜」というタイトルでご講演いただいた.木下氏が前年度,企業等から受けてGCを活用した相談案件の約9割で熱分解装置が利用されていたとのことで,工夫した点を交え,様々な活用例についてご紹介があった.特に混合物など複雑な組成の試料で,熱分解装置が実用的で強力な手法になるということで,熱分解生成物とその由来との関連付けが重要になるとのことであった.折り良く「ぶんせき」誌の2022年10月号の<解説>に木下氏が「異物分析における熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法の活用」というテーマでご執筆されており,本講演内で紹介された.
続いて,都産技研・墨田支所 佐々木 直里氏から「におい嗅ぎGC/MSによる技術支援〜異臭分析、クレーム解析、研究事例の紹介〜」というタイトルでご講演いただいた.都産技研では異臭に関する相談は,佐々木氏が所属する墨田支所で対応しており,担当者は皆,臭気判定士の資格を有しているとのことであった.相談内容としては,カビ臭の相談が多いとのことであったが,カビ臭原因物質は木製パレット等からの汚染事例が多く報告されていることから,関連業者に対してこのような事例についてもう少し周知する必要があると強調されていた.また,実際にはカビ臭が原因ではないにも関わらず,いつもと違うにおいがするとカビ臭と思い込んでしまう事例も多いとのことであった.講演内では依頼試験以外にも,セミナーの開催や共同研究により企業を技術支援している事例が紹介された.
休憩を挟んだ後,都産技研・材料技術グループ 染川 正一氏から「触媒開発支援におけるマイクロGCの活用」というテーマでご講演いただいた.触媒開発は設備や試験にお金や人手がかかるため,大手の企業が中心となっているが,都産技研では,なるべく簡便かつ確実な方法で触媒の活性を評価し,中小企業を支援しているとのことであった.講演内で触媒評価にマイクロGCを用いる利点が紹介され,少ない分析量でも感度良く測定できる点,2〜3分程度で分析可能である点,長時間の反応でも自動化により容易に追従できる点が挙げられていた.活用例としては,熱では1000℃以上が必要な水の分解について,光触媒を用いて室温で分解を評価した事例等が紹介された.
講演会終了後,4グループに分かれて所内を見学した.今回の会場となった都産技研本部は2011年3月に臨海副都心青海地区に開設されたとのことであったが,10年以上が経過しているとは思えない程,綺麗な施設であった.講演会で異物分析についてご講演いただいた木下氏が所属される有機機器分析室では,実際の異物試料を見せていただいたが,目を凝らさないと分からない程,小さい異物もあり,このような異物分析は苦労が多いのではないかと思われた.また,放射線応用の研究室では,大型のX線透過試験室があり,試験室に入れば,大型の試料や重量物試料でも撮影可能とのことであった.ユニークな測定試料としては刀剣があり,「継ぎ茎(つぎなかご)」という作刀者の銘が切ってある茎にそれとは異なる刀身を継ぎ合わせる偽装手法の調査で使用されるとのことであった.見学に行く先々で機器や設備が非常に充実しており,東京都以外の企業等からも多くの相談が寄せられるというのも納得であった.
見学会終了後,GC懇委員長の佐藤先生からの閉会挨拶があり,解散となったが,その後も会場内で講師と熱心な参加者との間で活発な情報交換が行われた.参加人数を限定して久しぶりに開催された見学会であったが,対面で開催されるイベントの良さが感じられた会であった.最後に,本見学会・講演会にご協力及びご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます.
(東京都健康安全研究センター)坂本 美穂
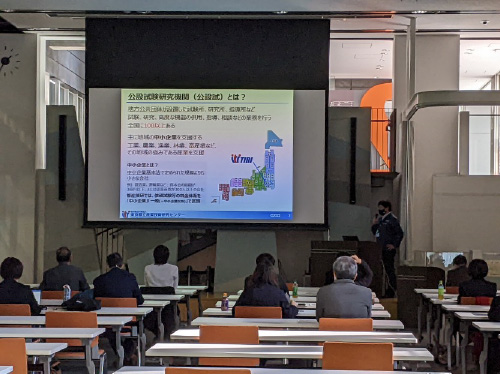
都産技研センター紹介時の講演会場の様子
日本分析化学会第71年会 ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会開催報告
日本分析化学会第71年会は岡山大学津島キャンパスにて2022年9月14日(水)〜 9月16日(金)にて開催されました。ガスクロマトグラフィー研究懇談会の講演会においては、国立文化財機構奈良文化財研究所・BioArCh, University of Yorkの庄田慎矢先生に御講演をいただきました。コロナ禍での開催で密を避けた座席配置ではありましたが、会場は満席となり約60名が聴講され、大盛況のうちに終了いたしました。
庄田先生には「ガスクロマトグラフィーを用いて食の過去を探る:近年の成果から」というタイトルで、近年飛躍的な進展を見せている、GCを用いた「考古生化学的研究」についてご紹介いただきました。
方法としては、土器などの考古遺物の内部にわずかに残存する土器片試料から胎土、付着物を採取・粉体化して脂質を抽出し、GC-MSを用いて残存脂質濃度の評価、生物指標化合物の検出、異性体比の測定、またGC-c-IRMSを用いて個別脂質の炭素安定同位体比を測定し、その地域に存在した土器の伝統、食生活習慣を解き明かされた研究内容について御紹介いただきました。具体的な成果として、日本や朝鮮半島、ロシアアムール河下流域、中流域、中国長江流域などで新石器時代の土器を分析され、それぞれの地域で異なる土器使用の伝統が存在したことを示された成果、キビPanicum Miliaceumの生物指標を土器胎土から検出された成果、素焼き土器に限られていた分析対象を窯焼き土器に応用された成果について紹介いただきました。御発表の時間は限られていましたが、聴衆からも「土器の保存状態などによっては物質が残っていないこともあるのか?」「土器の分析はバラツキも出てくるのか?」などの多くの質問があり、その関心の高さが伺えました。
GCにて分析を進められた研究内容でありましたが、検出された物質から描かれ膨らむ当時の生活様式描写には、同じ研究者として大きな夢とロマンを感じました。今後さらに様々なことが明らかになっていくことが期待される研究でありますとともに、今後の展開が大変楽しみになる御講演でありました。
(酒類総合研究所 岸本徹)
第377回ガスクロマトグラフィー研究懇談会講演会
開催報告「主題:検出器の最新技術と基礎を学ぶ」
2022年6月24日(金)、北とぴあ飛鳥ホール(東京都北区)にて第377回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会が開催された。本研究懇談会では毎年度初回の時期に基礎的な内容を主体とした講演会を催しており、今年度は「検出器の最新技術と基礎を学ぶ」というテーマのもと、運営委員の和田、木下、坂本が幹事を務め、プログラムは以下に示すようにGC検出器に因んで主題講演2題のほか、基礎講座1題と技術講演3題から構成された。また、本講演会は会場聴講ならびにオンライン聴講のハイブリッド形式で実施され、合計で約70名が参加した。全面的ではないものの、会場対面形式の実施は2019年11月以来であった。会場では講師や関係者が会場に資料を並べ、本会の佐藤委員長も2年半ぶりに長崎から東京に来て会場で開催挨拶して久々に参加者・講演者等との情報交換も行えた。
プログラム(13:30~16:40)
【主題講演】
1. 超小型質量分析計MX908の技術と化学剤検知 (エス・ティ・ジャパン)小林 恒夫 化学兵器の現場探知など危機管理製品として利用される装置として、高速GCとトロイダル型イオントラップ質量分析装置を一体化したポータブルGC-MSやターボポンプ不要な低真空質量分析法を活用した検出器が紹介された。現場利用で求められる要素である、電池利用や大気圧イオン化法、短時間測定を適えており、極微量レベルの検出も可能としていた。
2. ボールSAW(弾性表面波)センサの原理と超小型GCへの応用 (ボールウェーブ、東北大名誉教授)山中 一司 球状素子の多重周回する弾性表面波(SAW)を利用したボールSAWセンサが開発され、ボール表面にターゲットに合わせた感応薄膜をコートすることで、超微量な水分や水素の検知が実現されており、その技術をGC検出器へ発展させた装置について解説がなされた。MEMS技術が活用されたカラムと組み合わせることで手のひらサイズのGCが造られ、ppbオーダーの定量分析も達成している。適用例として、日本酒の香気成分の分析が紹介された。
【基礎講座】
3. GCの検出器と質量分析計の基礎 (アジレント・テクノロジー)中村 貞夫 選択性、感度、ダイナミックレンジ、応答感度など検出器としての基本的な特徴や主な検出器の原理のほか、質量分析計について基礎的な事項についての解説がなされた。
【技術講演】
4. 硫黄化学発光検出器(SCD)の原理と応用例 (島津製作所)長尾 優 硫黄に特異的な検出器であるSCDについて、装置の概要や他の特異的検出器と比較して、定量分析時の優位性などについて解説がなされた。
5. MS用キャピラリーカラムについて (レステック)内海 貝 低ブリードのMS用キャピラリーカラムについて、高分子量化、架橋、silarylene構造といった液相における特徴の解説のほか、PLOTカラムをMSにつなぐ際の注意点が紹介された。
6. 検出器特性を利用した同定法(PID、DELCD、RGD) (テクノインターナショナル)野口 政明 SRI社による検出器である光イオン化検出器(PID)、塩素および臭素に選択性をもつ乾式電気誘導検出器(DELCD)、還元性のガスを対象とした還元ガス検出器(RGD)について、各検出器の特徴ならびにクロマトグラムの違いが示された。
本講演会を通じて、GC検出器について再認識や新たな知見が得られたほか、最新技術を駆使した装置の小型化が進んでおり、新たな形でガスクロマトグラフィーが社会に活用される姿を感じ取ることができた。講演を予定していたSpectra Analysis社製GC-IR(DiscovIR)の紹介(ケン商品開発)高橋 慶氏のオンラインでの講演はweb接続のトラブルがありスライド切替が不調であったため、後日、録画した講演を参加者に聴講して頂くこととなった。最後に、本講演会の開催にあたり、ご講演をご快諾していただきました講師の皆様、ご来場ならびにオンラインにて聴講していただきました皆様に深く御礼を申し上げます。
〔(地独)東京都立産業技術研究センター 木下健司〕

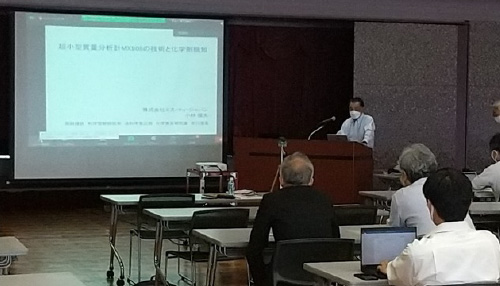
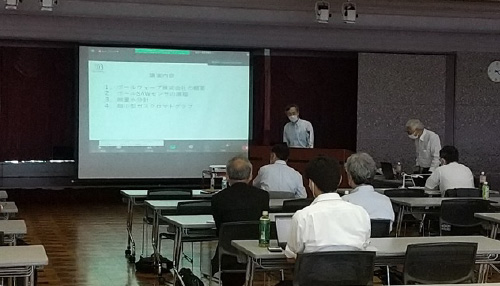
第376回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会
開催報告 「主題:持続可能な社会に役立つガスクロマトグラフィー 第1回」
第376回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会 開催報告 「主題:持続可能な社会に役立つガスクロマトグラフィー 第1回」 2022年2月18日(金)に第376回特別講演会を開催しました。例年、特別講演会は11月末〜12月初旬の開催ですが、2020年は開催を中止しており、この度、会期をずらしての2021年度最後にしてようやく実施することができました。
11月にWEB委員会を実施し2022年の計画を立てた結果、近年注目されているSDGsをテーマとした講演会のシリーズ化/過去に分析化学会年会や討論会で人気のあったリクエスト講演/ポスター発表/会場とオンラインのハイブリッド形式で開催、などを試みることとなりました。しかしながら、この2月の特別講演会は現在のコロナ禍の状況から当初予定しておりましたハイブリッド形式を断念してオンラインのみの開催とし、ポスター発表はショートプレゼンテーションに変更となりました。
さて、本講演会はSDGs第1回目として2.飢餓、3.保健、6.水/衛生、12.持続可能な消費と生産、13.気候変動、15.陸上資源 を中心とした講演を各分野の研究を行っている研究者の方々を講師としてお招きしました。また、運営委員所属団体によるショートプレゼンテーションでは、技術的な内容だけでなく、新しい製品紹介、施設紹介などの内容も含まれました。総合司会は、トレイジャンの大森委員が、各講演の座長は山上委員、内海委員、木下委員、そして日本電子の西島委員と生方氏が務めました。北とぴあの会場を使ったハイブリッド形式の試みと進行調整は前田副委員長他が行いました。
WEB配信は、2021年と同様の一般財団法人大気環境総合センター様のシステムを利用し、北とぴあに来ていただける講師が集まって会場から行いました。参加者は定員の100名に達し、大変盛況でした。
〔主題講演〕
1題目の講演は、シャトー・メルシャン椀子ワイナリー 小林弘憲先生でした。小林先生には2015年5月に山梨大学で開催された「分析化学討論会特別講演会セパレーションサイエンス特別講演」でワイン香気についてお話をいただいており、そのリクエスト講演となりました。前半は、ワインの香り(フレーバー、アロマ、ブーケ等)のコントロールのお話を、後半は現在携わられている椀子ワイナリー建設について紹介いただきました。 ワインの香りは、甲州ワインのネガティブ/ポジティブアロマについて説明がありましたが、その中でもやはりチオール化合物の重要性や扱いの難しさを再認識させられました。2000年当時から「良いワインは、良いブドウから」、「まずブドウありき」を合言葉に取り組んできたワイナリー建設、そして椀子ワイナリーの3つの使命である「地域との共生」「自然との共生」「未来との共生」については、ぶどうや酒類関係者だけでなく、わたしたち地球に生きるすべてのヒトが見つめなおすべきテーマであると感じました。
2題目は、大阪大学生物工学の古野正浩先生の食品メタボロミクスのお話で、2021年9月にオンライン開催された「分析化学会年会」のリクエスト講演でした。古野先生は、そのセパレーションサイエンスの広く深い知識と、現在の研究職の両方の観点から、市販の捕集剤や極性カラムについて製造メーカーへの改善点などについてお話しくださいました。参加していたラボ製品メーカーにとっては耳の痛い話もありましたが、このようなご講演ができるのも古野先生ならでは、です。聴講者にとって、参考になる話題が詰め込まれた40分でした。
3題目の森林総合研究所の松原恵理先生のご講演は「香りでつなぐ人の生活と森の循環」という魅力的な演題でした。松原先生は、ヒトの身体やココロをはかるのがお仕事ということで、木材の香りの分析と人への効果などについて、森林総合研究所の紹介と併せてご説明いただきました。間伐作業の重要さやその再利用、また、スギ材やヒノキ材また、クロモジ茶の香りの人への生理心理学的な効果に関する研究は、働き方が大きな変化を遂げた昨今、間違いなく新たに再注目するべき重要なテーマであると実感しました。更に、近年、森林総合研究所で取り組まれている蒸留酒と醸造酒の消費者テストを毎年11〜12月に開催しておられ、どなたでも参加可能とのことでした。
最後の講演は東海大学理学部の関根嘉香教授のヒト皮膚からの発生ガスのご講演でした。関根先生には2019年の日本分析化学年会で御講演後、反響があったため今回の講演会のトリをお願いしました。皮膚から出るガスが、生活環境、精神状態、その他によってかわるということで、中年男性のジアセチルやノネナール、ダイエットによるアセトン、アルコール代謝のアセトアルデヒド、喫煙者のニコチン、アンモニアはメンタルや体が疲れた時、など家族や周囲の大切な人の変化に気づくためのヒントについてレクチャーいただきました。「皮膚ガスは心と体の静かなる声」とは関根先生のお言葉ですが、身近な人のにおいが変わった際には「くさい」などと言わずに相手を気遣うべきなのかもしれません。
〔ショートプレゼンテーション〕
招待ショートプレゼンテーションでは、2018年の日本分析化学年会で御講演頂いた山中先生が設立したボールウェーブ社/東北大学ベンチャーの赤尾慎吾先生による手のひらサイズのGCを用いた日本酒香気成分分析について紹介いただきました。検出器には革新的なボールSAWセンサの技術を用いており、更に香気成分の濃縮システムと分離カラムを内蔵した、全く新しいタイプの小型GCでした。日本酒の醸造工程の品質管理や酵母育成開発における生成物質の現場での分析の適用が期待されます。講演会終了後にデモンストレーションも行ってくださり、オンライン研究会であるにもかかわらずライブ感を楽しむことができました。
運営委員所属団体によるショートプレゼンテーションは9演題あり、1.アイスティサイエンスの松尾委員からはオンラインSPE-GCを用いたメタボローム用前処理自動化技術、2.フロンティア・ラボの渡辺委員から極性におい成分分析用固相抽出素子、3.玄川リサーチは羽田からハチミツ分析例、4.Restekの内海委員より高速GCカラムキット、5.ジーエルサイエンスの武田氏からは皮膚ガス簡易捕集法の紹介、6.トレイジャンの大森委員による新製品カラム、7.西川計測の小野氏からはSDGsに向けた香気分析について、8.佐々木氏からは東京都立産業技術研究センターで実施している匂い分析例、9.日本電子の生方氏によるGC-TOFMSの紹介がありました。
今回の特別講演会は、初の試みずくめで幹事を務めさせていただいた大森委員はじめとする古野委員、私他運営委員も戸惑いながら準備を進めてまいりました。申込時点から当日のWEB開催まで、スタッフが不慣れな中、講演中チャットやメールでアドバイスをくださった参加者の皆様に心よりお礼申し上げます。また、運営にご協力いただいた(一財)大気環境総合センター様にこの場を借りて御礼申し上げます。今後、会員の皆様のポスター発表も検討していく所存です。多くの研究者がガスクロマトグラフィー研究懇談会を通じて、今までより一層活発な討論を行い交流できることを願っております。
ガスクロマトグラフィー研究懇談会 運営委員
(玄川リサーチ)羽田三奈子
第375回ガスクロマトグラフィー研究懇談会研究会
開催報告 「主題:コロナ禍のもとでの研究活動」
本研究懇談会では、コロナ禍のなかで、新たな試みとしてWebセミナーを行う事で活動を継続し、普段研究会に参加できない地方の会員の参加を得る等一定の成果を上げつつあります。昨年度の2021年2月に開催したオンライン形式での研究会をはじめ、6月開催の第373回研究会では運営委員の役割を忘れないよう、運営委員の紹介があれば学生も参加できるようにしました。初回は録画の配信のみ、2回目は配信元からライブ配信を加え、3回目になる今回は録画配信に加えてリモートでの講師参加も試みました。参加者も、運営委員の紹介があれば学生と(公社)日本分析化学会会員の参加もできるようにしました。また、直接会う事が難しい中で、コミュニケーションを図る事ができるよう、講演毎に質疑応答や情報交換する事も試しました。
今回の研究会の主題として、貴重な記録としてコロナ禍での運営委員の研究、研究活動、研究室運営等を紹介する企画とし、企業の方からはコロナ禍でのラボワークやワークスタイルの変化に関連した話題を提供いただき、会員の方に情報提供しました。3時間にわたる研究会は3部にわかれ、研究活動紹介1として3題が提供されました。講演題目と演者は、「長崎国際大薬学部 佐藤研究室の研究と研究活動紹介(長崎国際大)佐藤博」で、研究室での学生の研究状況や現在すすめている研究・研究室の機器紹介等盛りだくさんの内容でした。「コロナ禍におけるガスクロマトグラフィーに関連した取り組み —都産技の技術相談を中心に紹介—(都産技)木下健司」では、東京都産業技術研究センターの簡単な紹介の後、コロナ禍での技術相談対応や相談案件を見越しての予備検討の紹介があり、相談件数は対応策ができた後では対策前より増加傾向にあるとの事で、中小企業向けの相談を止めない工夫の成果が出ていました。「コロナ禍における山梨大学の講義・研究活動について(山梨大)植田郁生」では、研究室の研究内容は6月に報告されたので、主に、山梨大学全体の対応や、研究室として可能な限り対面での実習や講義を続ける努力が紹介されました。学外での活動、特に必修となっている学会参加と報告について、2年間リアルな学会開催がなく、従来の学会活動を経験しないまま卒業してしまう学生が出てしまったことは印象的でした。
企業からの、コロナ禍でのラボワークに関連した話題提供として3題が提供されました。「COVID-19がもたらした共同研究などに関わる変化(フロンティア・ラボ)渡辺壱」では、企業の活動紹介の後、研究開発型企業として実施している国際共同研究の変化が紹介されました。ロックダウンが続く中、現地のスタッフが果たす役割や、研究計画そのものの遂行に時間がかかるなかで研究成果を得る事の困難さなどが伝えられました。「コロナ禍でのワークスタイルの変化(アサヒビール)舛田晋」では、管理側からの視点でリモートワークを行う中でのラボ運営やスタッフとのコミュニケーション維持、メンタル面での配慮などメリット・デメリットなど、現場の状況を紹介いただきました。定期的に事務室に集まる時間を作りコミュニケーションを図る取り組みなどの配慮は大切であると感じました。「リモート・ローテーションワークに貢献する前処理自動化技術(アイスティサイエンス)松尾俊介」では、ラボ分析を効率よく行う為に役立つ前処理の自動化技術が紹介されました。時間がかかる前処理を自動化し、処理済みの試料をオンラインで分析に供する事で実験室に滞在する時間を有効に活用する為に役立ち、コロナ禍が収束した後も有効な技術と感じました。
最後の研究活動紹介2として3題提供され、「ガスクロマトグラフィー関連の研究と研究活動紹介(産総研)渡邉卓朗」では、研究室の簡単な紹介の後、組織の対応が研究を実施する現場に大きな影響を与えている例等が紹介されました。国際ビジネスでは日常的であるが、国際会議がオンラインになり移動時間は無くなったが時差のおかげで深夜の会議が増える事でストレスが増いるようでした。「日大生産工学部中釜研究室の研究と研究活動紹介(日大工)中釜達朗」では、Webでの講義資料の作成や受講者の理解度確認のためのレポート提出と確認等、受講の自由度が増した分提出物が増え、教える側も学生側も負担が増えた様子等が紹介されました。役に立つ教材作成と研究概要も紹介され興味深い内容でした。「酒類総合研究所でのガスクロマトグラフィーを活用した技術開発について(酒類研)岸本徹」では、財務省の研究所としての独特な研究について紹介され、研究活動の持続と成果紹介が行われました。将来につながる研究は技術移転が課題で、移転先との交流が回復するのを待つとの事です。
最後に委員長から、講師を含めて約50名の参加があり、参加頂いた方々に謝意を表明して終了しました。 WEB会議システムにご協力いただいた一般財団法人 大気環境総合センター様に心より御礼申し上げます。
ガスクロマトグラフィー研究懇談会 副委員長
((元)産総研) 前田 恒昭
第373回ガスクロマトグラフィー研究懇談会 研究会 開催報告
日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会(以下GC懇)は、2021年6月25日(金)に第373回研究懇談会・講演会を開催しました。今回の主題は「主題:ガスクロマトグラフィーの新刊紹介と前処理の新技術」で、基礎を学ぶための教科書として「ガスクロ・ガスマス自由自在」(丸善出版)の出版を予定しており、出版に先立ち紹介する事と、ガスクロマトグラフィーの前処理とその新技術の紹介を合わせて講演会を構成しました。
GC懇としては2月の総会、講演会に引き続き、オンライン形式(Webセミナー)での開催となり、講演者・聴講者ともリモートでの参加となりました。
<基礎講座1> 「ガスクロ・ガスマス自由自在(丸善出版)の新刊紹介」という題で、元産総研の前田副委員長に講演していただいた。内容は2部構成で、最初に、本新刊の構成から簡単な内容の紹介があり、その後監修時の留意したこと等を紹介していただいた。ガスクロマトグラフィー教科書は少なく、貴重な教科書として活用されると思います。秋頃には出版できるようです。
<基礎講座2> 基礎講座の2番目は、「ガスクロマトグラフ分析に活用されている固相抽出法の基礎」という題で、ジーエルサイエンスの三浦様に講演していただいた。固相抽出法の原理、操作例、応用から、SPMEやシリカモノリス固相剤の紹介までわかりやすく、詳細にご説明していただきました。
<主題講演>「ガスクロマトグラフィーの新技術」
講演1は、「固相抽出型デバイスによる空気中VOCとSVOCのGC分析」という題で、山梨大学の植田先生に講演していただいた。研究室の紹介映像が最初にあり目が引き付けられました。、繰り返し使用でき、少量の溶媒で抽出可能な固相抽出捕集デバイスを開発され、適用例を紹介いただきました。大気や室内環境中の多感芳香族、フタル酸エステル類、揮発性抗がん剤等の分析が、簡便かつ安価に実施できるという大変興味深い講演でした。
講演2は「分配型捕集剤を充填したNeedlExによるSVOC分析」という題で、信和化工の藤村様に講演していただきました。 針先内部に微小の吸着剤を充てんし、GCの注入口で熱脱着させる分析法で、従来使用されているメソポーラス吸着剤に代わり分配型捕集剤を充填することで、水中のTexanol、TXIBといったSVOCを捕集、分析する事例を紹介されました。大変面白い講演でした。
講演3は「低温濃縮について」という題で、ピコデバイスの津田様に講演していただきました。低温濃縮の基礎的なお話に続き、少量のガス中のVOCを、吸着材を使わず低温にて濃縮、加熱脱離できるデバイスについて講演していただきました。濃縮するガス量も少量で、濃縮時間も短く利点の多い、非常に面白いデバイスのお話でした。
今回も前回の総会・講演会に続きオンライン形式での開催となりました。80名を超える参加者に出席いただきました。各演題とも短時間の講演でしたが、コンパクトにまとまった、非常に面白い講演会でした。 WEB会議システムにご協力いただいた一般財団法人 大気環境総合センター様に心より御礼申し上げます。
ガスクロマトグラフィー研究懇談会 副委員長
((株)島津製作所) 和田 豊仁
第372回ガスクロマトグラフィー研究懇談会 研究会 開催報告
日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会(以下GC懇)は、2021年2月19日(金)に第372回研究会を開催した。今回の主題は「ガスクロマトグラフィーで用いるヘリウムガスの供給に関する話題と技術的対応」であり、ヘリウムの供給の現状から対応策等が紹介された。またGC懇としては初の試みとなるオンライン形式(Webセミナー)での開催となり、講演者・聴講者ともリモートでの参加となった。
基調講演では「ヘリウムの将来と展望」と題して日本エア・リキードの田首裕一朗氏より「ヘリウムの将来と展望」の講演を頂戴した。
ヘリウムは様々な分野で使用されており、ガスクロマトグラフィーに代表されるキャリヤーガス以外に、最近では半導体の製造工程、MRIやNMR測定、宇宙分野におけるロケットなど冷却を目的に使用されており、これらの産業分野で年間に3-4%の需要増加が予想されている。
ヘリウムは世界で産地が限定されており、米国、およびカタールが大部分を占めている。供給が滞る主な原因は老朽化したプラントの定期修理中のトラブル、あるいは米国のヘリウム戦略による備蓄である。2021年にロシアで新しいプラントが稼働して生産が開始される予定で、しばらくは供給が需要を上回ると予想される。これらの理由から、グローバルなヘリウムの調達が重要であり、サプライチェーンの構築が今後のヘリウム安定供給の課題である。
主題講演としては、GCメーカー二社より主に「対策」について講演いただいた。
「GC/MSにおけるHe削減と代替キャリヤーガスについて」 (アジレント・テクノロジー) 姉川 彩氏
「GCにおけるHe削減と代替キャリヤーガスについて」 (島津製作所) 和田 豊仁氏
ともに、日々の分析業務において「ヘリウムガスをいかに節約するか」と、「代替キャリヤーガスを使用する際のポイント」について講演され、姉川氏からは特にGC/MSにおいて代替キャリヤーガスを使用する際のポイント、和田氏からは各種GC検出器における代替キャリヤーガスの影響などについて詳しくご説明いただいた。
技術講演では、
1.キャリヤーガスを変更するとGC条件はどのように変更すればよいのか?
—条件設定とモデルクロマトグラムの確認ができるツールをご紹介—
(Restekコーポレーション) 海老原 卓也氏
ヘリウムガス以外のキャリヤーガスを使用するには、分析条件の最適化が必要となる。その為のメソッド変換ツールとして「EZGC Method Translator」と、データベースを活用したシミュレーションツールとして「
ProEZGC Chromatogram Modeler」が紹介された。
2.He代替水素キャリヤーガス対応、GC/GCMS用高純度ガス発生装置のご紹介
(ピークサイエンティフィックジャパン)鈴木 義昭氏
最新式の高純度な水素ガス発生装置「PRECISION」シリーズ、およびゼロエアジェネレータについて紹介された。
GC,GC/MS分析において、ヘリウムガスは欠くことができず、すべてのGC用ガスをヘリウムから置き換えることは困難である。そのため、今回の発表のあった「ヘリウムガスの節約」と「代替キャリヤーガスへの対応」は、今後も継続的な課題として取り組む必要がある。講演いただいた演者各位には、貴重な情報を共有いただき、感謝いたします。
みとしてオンライン形式での開催となりました。通信環境維持のため、ご案内をガスクロマトグラフィー研究懇談会会員に限定させていただいた事、また質問は講演終了後講師に直接メールにてお問合せいただく形となった事をご報告いたします。通例の集合開催とは異なり、遠方からもエントリーいただくことができ50名超える参加者に出席いただくことができました。今後GC懇の活動としての一つのモデルとすることができ、会議システムにご協力いただいた一般財団法人 大気環境総合センター様に心より御礼申し上げます。
(ガスクロマトグラフィー研究懇談会 副委員長,アジレント・テクノロジー(株))川上肇