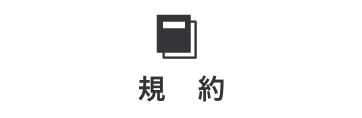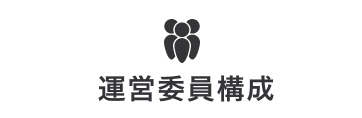2019年度
第370回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会開催報告
2019年11月22日(金)、北とぴあ飛鳥ホール(東京都北区)にて第370回ガスクロマトグラフィー研究懇談会特別講演会が開催された。本研究懇談会では毎年年末近い時期に特別講演会を催しており、今年度は「科学と文化に貢献するガスクロマトグラフィー−人を知る、地球を知る、宇宙を知る−」の壮大なテーマのもと、プログラムは以下に示すように多分野にわたる内容の主題講演5題のほか、装置関連メーカー各社による技術講演5題から構成された。10:00から17:00までと長丁場であったものの、聴衆から高い関心が寄せられていた。
理化学研究所高橋様による主題講演「極微量の硫黄同位体比分析による、遺跡から出土した水銀朱の産地同定」では、基準物質に対する硫黄の同位体比(34S/32S)の算出をベースとした分析手法が示された。また、特に古代遺跡品のように採取量が限られる試料を分析するための改善策として、2段階のクライオフォーカシングを駆使した高感度化や硫黄を含まないテープを使ったサンプリング方法が紹介された。東北大学古川様による、最近新聞やテレビ他各方面から取材されホットな話題でもある「宇宙有機物と生命分子の起源」の講演では、生命の起源を探る背景や経緯について解説され、生命に関する有機化合物の調査にはクロマトグラフィーが必要不可欠であり、誘導体化法を駆使した解析の他、熱分解GCやGC-燃焼-同位体比質量分析などが試行されている状況を把握することができた。また、現状の課題としてキラル分離が挙げられ、今後のさらなる生命分子の起源解明が期待された。京都大学防災研究所佐々木様による「ドローンを活用した環境計測技術の新展開」では、通常空撮で利用されることの多いドローンを環境測定に応用する取り組みが行われており、従来のラジオゾンデを利用した方法では得難いデータ採取のためのモニタリングについて紹介された。現状では依然としてドローンの性能不足などいくつか課題があるとのことで、ドローンの発展に伴い本分野の発展が予想された。京都大学地球環境学堂田中様より、各方面で話題となっているマイクロプラスチックに関する講演「都市水環境系におけるマイクロプラスチックの挙動と微量有機化合物との関係」がなされ、マイクロプラスチックを取り巻く環境や動向、吸着する化学物質が示されたほか、実際の現場には煩雑で非常に手間のかかる作業が必要であり、調査するうえでの難しさや奥深さが感じられた。本講演会の最後として森林総合研究所大平様による主題講演「健康に役立つ森林の香り・木材の香り −最新の利用技術について‐」が行われた。新聞記事等を通じて森林浴のリフレッシュ効果や抗がん力改善効果が知られており、それには精油に含まれているテルペノイドが関与しているといわれる。森林や建築木材における特徴的なテルペノイド種の違いや健康増進機能への関与、消臭脱臭作用について示された後、環境負荷の小さい精油抽出法として開発された減圧式マイクロは水蒸気蒸留法の紹介がなされた。本抽出法により、これまでほとんど処分されていた植物枝葉は精油や抽出水、抽出残渣に分画され、さらにそれぞれが利用価値を有していて、空気質改善剤や消臭剤への商品化が実現されており、今後の日本の森林資源の利用価値拡大への展望が感じられた。
その他に技術講演においては、GC分析では誘導体化が必要となるアミノ酸や有機酸など極性化合物について、イオン交換固相抽出と誘導体化を組み合わせた固相誘導体化法ならびにその自動化システムの紹介(アイスティサイエンス 松尾様)やカラム用充填材に使用するケイソウ土における供給状況と別途開発されたマクロポーラスシリカの性能(信和化工 藤村様)、テルペノイドの分析方法に関する話題(Restek 岡村様)、大気中の窒素を利用する新規イオン源を用いたリアルタイム分析による長時間モニタリングの試行(エーエムアール 坂倉様)、感知閾値がppt、ppqオーダーとなるカビ臭分析を想定した高感度化のためのテクニック(サーモフィッシャーサイエンティフィク 土屋様)という多岐にわたる話題について新たなアプローチの紹介がなされた。
本講演会を通じて、考古学や宇宙科学、環境科学など広範囲にガスクロマトグラフィーが社会へ貢献している一端を窺い知ることができた。講演会終了後には、講演者を含め意見交換会が行われ、親睦を深めつつ有意義な情報交換がなされた。最後に、本講演会の開催にあたり、ご講演をご快諾していただきました講師の皆様、ご来場いただきました皆様に深く御礼を申し上げます。
〔(地独)東京都立産業技術研究センター 木下健司〕

第370回講演会写真
第366回ガスクロマトグラフィー研究懇談会 講演会・見学会開催報告
2019年7月5日(金),東京都健康安全研究センターにおいて,標題の講演会・見学会が開催された.当センターの都合により参加人数を約30名に限定しての開催となった。
開会挨拶では,GC懇委員長の佐藤先生(長崎国際大)から当センターとGC懇との関わりについてご紹介があり,元当センター職員の故竹内名誉会員(元委員長)や水石名誉会員(元副委員長)の懐かしい名前が挙がった。
講演の初めに,当センター薬事環境科学部 守安貴子部長から当センターについての紹介があった。紹介の中で,当センターの前身が東京都立衛生研究所であること,平成15年の組織再編により現在の名称に改称されたこと等が紹介された。これを受けて参加者の方から「昔の都衛研でしたか」とお声がけいただき,改めて「都衛研」の名称が多くの方に親しまれていたことを実感した。当センターの組織及び業務内容は主にDVDで紹介されたが,その業務内容は感染症や食中毒の原因究明から食品・医薬品・環境に関する理化学分析,危険ドラッグやコンタクトレンズ等を対象とした生体影響試験など多岐に渡ることから,参加者からは「色々なことをやっているんですね」という感想の声が寄せられた。DVDによる紹介の他,具体的な危機管理対応事例として平成29年1月に問題となったC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」偽装医薬品事件が紹介された。事件当時も話題になったが,ハーボニー配合錠1ボトルが150万円の価格であると紹介されると会場内がどよめいた。偽造品の中にはビタミンを含有する錠剤が入れられたボトルもあり,このような問題のある製品を市場から速やかに排除することで,都民の生命や健康を守っていることが紹介された。
続いて,当センター薬事環境科学部環境衛生研究科 斎藤育江副参事研究員から「空気中のフタル酸エステル類測定法−衛生試験法・注解 空気試験法の改定−」というタイトルで講演があった。講演では,現在,厚生労働行政推進調査事業費補助金で行われている「化学物質リスク研究事業」の一環として取り組んでいる「室内空気環境汚染化学物質の標準試験法の策定およびリスク低減化に関する研究」での検討内容が紹介された.主に空気捕集用サンプラーとフタル酸ジイソノニル(DINP)及びフタル酸ジイソデシル(DIDP)の分離定量法の検討結果について紹介があり,特にDINPとDIDPはフタル酸エステル類の中でも異性体が多く,m/zが共通で,保持時間が一部重なることからISOでも標準試験法が設定されていない難しいテーマであると説明があった。会場内には実際にフタル酸エステル類の測定を経験している参加者も多く,溶媒や装置由来のフタル酸エステル類の低減方法に関する議論や試験法の設定が難しいDINP及びDIDPの分離定量法に関する多くの意見やアイデアが出され,活発な討論が繰り広げられた。
最後に,当センター薬事環境科学部医薬品研究科 中嶋順一主任研究員から「危険ドラッグ等の行政試験で活用されるGC-MSの分析例」が紹介された。講演では,植物片に合成カンナビノドを混入したいわゆる「脱法ハーブ」に関する分析例が紹介され,規制薬物の構造の一部を変えた未規制薬物が次々と出現する中,NMRや単結晶X線構造解析装置を用いて未規制薬物の構造を決定し,規制へと導いた事例が取り上げられた。また,現在,2,300以上もの規制薬物が存在する中,迅速に規制薬物を分析するためには,GC-MSライブラリーが不可欠であることにも触れられた。最近の事例としては,植物粉末からコウボク(ホオノキの樹皮)が検出された事例が紹介された。これに絡めて生薬に関するクイズが出されるなど,所々に参加者を和ませるようなトピックスが入った講演であった。先の講演の討論が非常に活発で,本講演の質疑応答時間が取れなくなってしまったが,その後の休憩時間中,「このような危険ドラッグはどこで作られているのか?」など演者と複数の参加者との間で熱い議論が展開された。
講演会が終了した後,環境衛生研究科,医薬品研究科,残留物質研究科の3研究科を3グループに分かれて見学した。各研究科では組織や業務に関する簡単な説明があり,分析装置が置いてある機器室等を見学した。環境衛生研究科では鑑別用に飼育されている蚊媒介感染症を引き起こす蚊が飼育されている様子や2011年3月の東日本大震災以降,注目された空間放射線量を測定するモニタリングポスト,医薬品研究科では生薬切片の顕微鏡画像や生薬保管庫などが紹介された。
意見交換会は都庁の職員食堂に場所を移して開催された。少し曇ってはいたものの,高層ビルの32階からの眺望は良好で,参加者が大きなガラス窓越しにその眺望を楽しんでいた。見学会場から30分以上徒歩で移動したこともあり,乾杯のビールはいつも以上に美味しく味わうことが出来た。また,東京都の蔵元澤乃井の地酒が人気で,涼しげな水色の瓶が次々と空いた。分析談義も大変盛り上がり,予定の終了時刻が過ぎても続けられる程,有意義な会となった。最後に,この場を借りて,本会にご協力,ご参加いただいた皆様に心より御礼申し上げます。
(東京都健康安全研究センター)坂本 美穂

東京都健康安全研究センター見学会
第365回ガスクロマトグラフィー研究懇談会 講演会開催報告
2019年5月31日に第365回ガスクロマトグラフィー研究懇談会 講演会が、王子の北トピア 飛鳥ホールにて開催された。
例年、年度初めの講演会は基礎講座を主に行っており、GC分析の基礎や試料調製などの手順について基礎的な知識を深めていただくのが目的である。今回の講演会は、「基礎講座 知っておくべきGC分析の基礎知識」−ガラス器具、天秤の取り扱いと検出器の基礎について−という題で、ガラス器具、天秤の取り扱いからはじまりGC分析の基礎的な話まで多岐にわたる講演を集めた。
参加者は約90名と盛況であった。
最初の講演は「誤解、間違いの多い理化学用ガラス機器の知識と取り扱い」という題で、 柴田科学 坂元様に講演いただいた。ガラス器具の特性や、計量器具の加熱の可否等、普段あまり聞くことのできない話、実験前に知っていなければならない話を分かりやすくお話しいただき、大変ためになる講演であった。
次の講演は「天秤の取り扱いについて 」という題で、島津製作所 越様に講演いただいた。電子天秤の特性、秤量値に影響を与える要素、校正の仕方、上手に使うコツ等、詳細に説明をしていただいた。実験室に必ず一つはある天秤だが、改めて使い方を聞くことはほとんどなく、非常にためになった。
3題めは「GC検出器の概要」という題で、アジレントテクノロジー 加賀美様に講演いただいた。最初にHe供給の現状および代替ガス等のお話、その後、検出器の特性について説明いただいた。He供給問題は最近の大きな課題でタイムリーな話であった。検出器の概要は、ほぼすべての検出器をわかりやすく説明いただいた。
4題めは「大きな声では言えない分析プチ情報」という題で島津製作所 和田(副委員長)が講演した。主にぶんせき誌2007年に寄稿された「入門講座 失敗から学ぶ分析技術のコツ」の一部紹介、「2010年セパレーションサイエンス座談会」の事例紹介、分析プチ情報の紹介を行った。
技術講演2題はいずれも基礎的な内容であった。はじめは「GCカラムの基礎」という題でRESTEKコーポレーションの 内海委員に講演いただいた。キャピラリカラムの基礎的な話を分かりやすくお話しいただいた。次は「GCにおける前処理」という題でGLサイエンスの馬場様が講演された。固相抽出などの前処理法、GCに接続するオプション等をわかりやすく説明していただいた。
いずれの講演も聴講者は熱心に聴講されており質問も活発であった。
講演終了後は意見交換会にて議論を深められた。
年に1回の基礎講座であるが、GC分析にとどまらず、どの分析でも共通する話も多く、満足度の高い講演会であった。
(株)島津製作所 和田豊仁

第365回研究会開場風景