評価法 〜ヒ素化合物の免疫作用について〜
(東京薬大、生命科学、環境衛生化学)○櫻井照明、藤原祺多夫
[連絡者;櫻井照明]
環境ホルモンの概念が紹介されてから、今まで比較的安全であるとされていた化学物質も内分泌撹乱作用や免疫作用などの生理作用を持つ事が明らかとなった。多くの研究により、内分泌撹乱作用についてはin vitro 評価法が確立されつつあるが、免疫作用については確立されていない。我々はマクロファージという免疫細胞を用い、化学物質の添加による細胞機能の変化を多面的に観察する事で、その物質の未知なる免疫作用を in vitro で効率良く評価、推定できる実験系を提案する。マクロファージは異物を貪食し、それを消化、断片化して抗原としてリンパ球に提示する代表的な免疫細胞である。さらに異物に反応するとアメーバ様のダイナミックな形態変化を示すので、化学物質の影響をin vitroで観察するのに適している。我々はこの細胞にインターフェロンとエンドトキシンという細胞活性化物質を少量添加する事で、異物に対する反応性を高め、実験に用いた。今回は、生体内での毒性発現機構が未解明なヒ素化合物を試料とした実験例を紹介する。
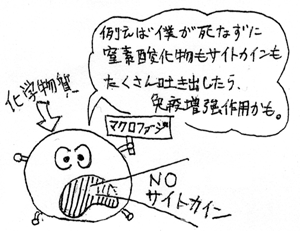 無機ヒ素を細胞に添加した場合、50%細胞致死濃度(IC50)は5μMであり、誘導された細胞死は壊死(necrosis)様であった。一方、無機ヒ素のヒトでの最終代謝(メチル化)産物であるジメチルアルシン酸(DMA)のIC50値は5mMで、興味あることに誘導された細胞死は自殺(apoptosis)様であった。また 無機ヒ素、DMA 共にマクロファージからの窒素酸化物の産生放出は抑制したが、炎症性サイトカインの放出は無機ヒ素で顕著に増加し、DMAでは逆に抑制された。以上より、無機ヒ素は免疫細胞に対し強い毒性を持ち、炎症性因子の放出を伴うnecrosisを誘発して生体を炎症状態に導くことが推測された。一方、メチル化ヒ素は免疫細胞に対する毒性が弱く、高濃度で細胞死を誘導するものの、それは炎症を伴わないapoptosisであることが明らかとなった。従って、ヒ素の生体内メチル化代謝は一種の解毒機構であると推定された。
無機ヒ素を細胞に添加した場合、50%細胞致死濃度(IC50)は5μMであり、誘導された細胞死は壊死(necrosis)様であった。一方、無機ヒ素のヒトでの最終代謝(メチル化)産物であるジメチルアルシン酸(DMA)のIC50値は5mMで、興味あることに誘導された細胞死は自殺(apoptosis)様であった。また 無機ヒ素、DMA 共にマクロファージからの窒素酸化物の産生放出は抑制したが、炎症性サイトカインの放出は無機ヒ素で顕著に増加し、DMAでは逆に抑制された。以上より、無機ヒ素は免疫細胞に対し強い毒性を持ち、炎症性因子の放出を伴うnecrosisを誘発して生体を炎症状態に導くことが推測された。一方、メチル化ヒ素は免疫細胞に対する毒性が弱く、高濃度で細胞死を誘導するものの、それは炎症を伴わないapoptosisであることが明らかとなった。従って、ヒ素の生体内メチル化代謝は一種の解毒機構であると推定された。