(山梨県環境科学研1・科学技術振興事業団2)○京谷智裕1,2・輿水達司1
[連絡者:京谷智裕]
毎年春になると中国大陸より飛来する、日本人にとって身近な風物詩でもある黄砂には、地球規模での気候変動の謎を解く鍵が隠されている。近年、東アジア地域での気候変動が黄砂の発生量に反映されているとの指摘がなされ (黄砂の発生量が多い=乾燥⇒寒い、黄砂の発生量が少ない=湿潤⇒暖かい)、地球温暖化の問題に対する一つの研究方針として、海底・湖底堆積物を用いて時代を追った黄砂量の変動を明らかにし、古気候を復元しようとする試みがなされている。しかし、通常、黄砂粒子の識別・定量には、バルク(平均) 組成のみが適用され、黄砂以外のバックグラウンド情報との識別には厳密さを欠く場合が多く、堆積物中の黄砂を定量する方法は確立されていない。さらに、従来のボーリングコアを用いた研究の多くは、千〜万年、短くても百〜千年の年代幅を単位とした気候変動を議論したものであり、もっと短い時間スケール毎での気候変動については不明な点も多い。
そこで我々は、まず黄砂粒子の新しい定量的な識別法を提案した。すなわち、大気エアロゾル (粒径10μm以下) 中の個々の石英粒子の不純物組成に着目すると、走査型電子顕微鏡 /エネルギー分散型X線分析法(SEM-EDX)により測定した個々の石英粒子の(Na2O+K2O)/SiO2(%)分布域は明瞭な
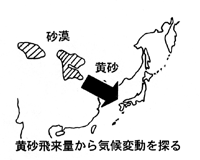 季節変化を示し、春季には、中国大陸の黄土や砂漠土のものに酷似する事を見出した。結局、個々の石英粒子を指標とすれば、日本の岩石・土壌由来の粒子から明確に識別して、粒子数として黄砂を定量できる事を明らかにした。現在、富士五湖において採取された過去数万年に遡るボーリングコアに本識別法を適用し、従来の研究よりはるかに短い数年単位 (1cm毎) での黄砂量の変動を読みとって、最終氷期以降の気候変動を解析している。既に、従来から指摘されているような百年スケールでの変動に加え、十年スケールでの寒暖のリズムを示唆する黄砂の変動パターンも検出しており、これまでは見えてこなかったより緻密な気候変動のリズムを明らかにして、古気候を高精度に復元することを目指している。
季節変化を示し、春季には、中国大陸の黄土や砂漠土のものに酷似する事を見出した。結局、個々の石英粒子を指標とすれば、日本の岩石・土壌由来の粒子から明確に識別して、粒子数として黄砂を定量できる事を明らかにした。現在、富士五湖において採取された過去数万年に遡るボーリングコアに本識別法を適用し、従来の研究よりはるかに短い数年単位 (1cm毎) での黄砂量の変動を読みとって、最終氷期以降の気候変動を解析している。既に、従来から指摘されているような百年スケールでの変動に加え、十年スケールでの寒暖のリズムを示唆する黄砂の変動パターンも検出しており、これまでは見えてこなかったより緻密な気候変動のリズムを明らかにして、古気候を高精度に復元することを目指している。