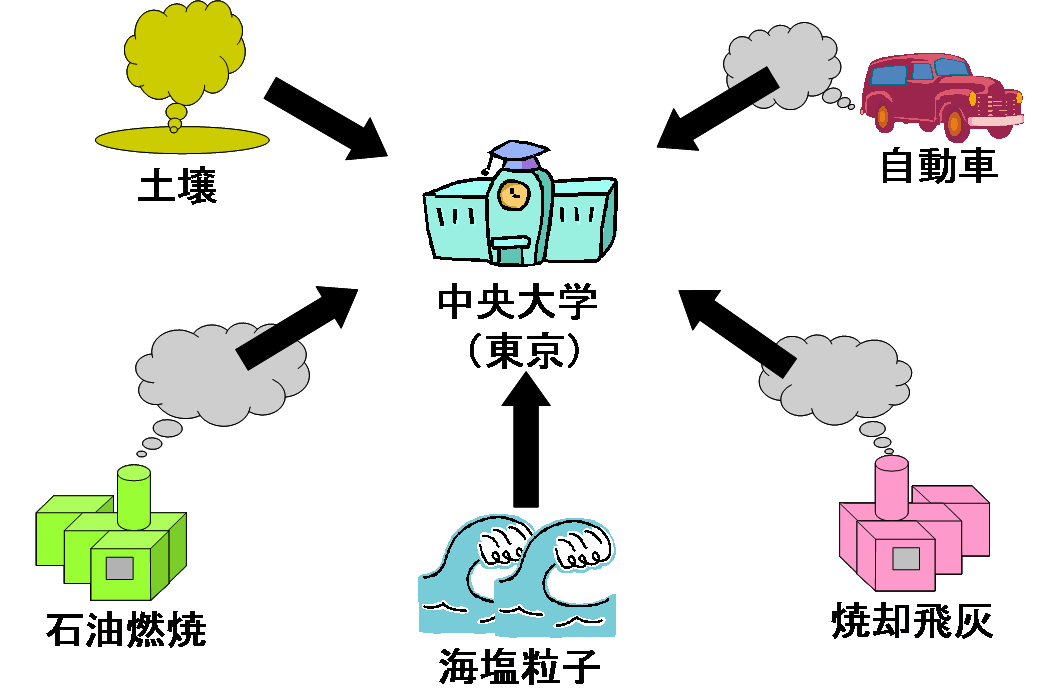【D1017】東京における粒径別大気粉塵の長期モニタリング結果から推察される発生源の解明
(中央大・理工)○木下幸・佐藤啓市・古田直紀
[連絡者:古田直紀、電話:03-3817-1906]
大気粉塵中でも特に粒径が< 2μmの微小粒子は肺への吸入や沈着による健康影響が懸念されている。また、アメリカで行われた疫学研究より、粒径が< 2.5μmの微小粒子の濃度と死亡率との間に相関があることが報告された(1993)。本研究室では、中央大学理工学部後楽園校舎内で1995年から継続して粒径別(< 2μm, 2-11μm, > 11μm)大気粉塵中の元素(主成分元素6元素、微量元素17元素)濃度を長期モニタリングしている。微量元素濃度をこれほどの長期に渡って、粒径ごとに測定している例は他にない。本研究では、11年間の測定結果から、大気粉塵中の元素の発生源を解明することを目的としている。そして、有害汚染元素がどのような発生源から放出されているのかを解明することによって、今後の大気汚染改善のための政策等に役立つことが期待される。さらに、現在、大気汚染に係る環境基準で、浮遊粒子状物質の総濃度についての規制はなされているが、元素濃度に関する規制はなされていない。ここで得られたデータは、今後元素濃度を考慮した環境基準を制定する際にも、重要な情報を与えてくれると考えられる。
測定した元素濃度から、元素の人間活動による汚染度を示す係数である濃縮係数を算出したところ、< 2μmの小さな粒径の大気粉塵中に有害汚染元素(Sb, Cd, Se, Pb, As)が多く濃縮していることが明らかとなった。その中でも、最も多く濃縮していた元素はSbであった。また、図に示すように、様々な発生源から中央大学で捕集した大気粉塵への寄与がどの程度か推定したところ、粒径が< 2μmの大気粉塵は自動車の寄与が大部分を占め、2-11μmでは土壌や海塩粒子の寄与、> 11μmでは土壌の寄与が比較的高い結果となった。Sbの起源として可能性のある種々の物質の分析結果、大気粉塵の1粒子計測の結果などを合わせて考察したところ、< 2μmの大気粉塵中のSbは、自動車のブレーキパッドから放出されている可能性が高いと考えられる。