FIA/ガス拡散装置の高機能化と環境分析への応用
樋口 慶郎(エフ・アイ・エー機器 )
樋口 慶郎(エフ・アイ・エー機器 )
FIAは実際分析における迅速,簡便,少試料・少試薬,自動化の容易さという利点の他に,“さまざまな前処理操作が流路の中で容易かつ再現性良く行なわれる”という特長を有している。加熱・恒温などの一般的な操作から,オンラインカラム濃縮・分離,溶媒抽出,酸化・還元などの前処理操作を精密に制御された流れを反応場とすることでバッチ法では到達できない高効率,高精度な前処理を実現することができる。本発表では前処理分離技術としてガス拡散法に着目し,FIA技術と組み合わせることで両者の利点を相乗的に高めるとともに環境試料の分析への応用についても報告する。
【2.ガス拡散装置の特徴】
ガス拡散/FIA法は測定対象が化学反応により特異的に気体を発生する系に限られているため,非常に高い選択性を有する。本研究ではまず,ガス透過効率の変動や,使用を繰り返すことによる透過機能の低下という従来からの最大の欠点を解決する装置を開発した。ガス拡散ユニット部の構造を図1に示す。ガラス管(内径2.1mm,外径6mm)の中に多孔質PTFEチューブ(内径1.0mm,外径1.9mm)を挿入した二重管構造になっており,多孔質PTFEチューブの内部を検出反応試薬が流れ,多孔質PTFEチューブとガラス管の間をキャリヤー溶液が流れる構造となっている。
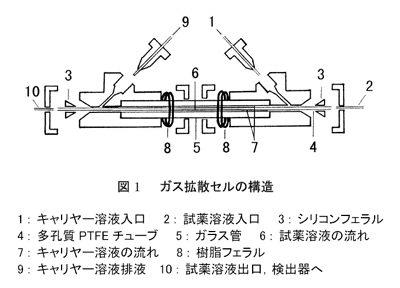
一方,気体の透過効率を一定に保ち,安定した再現性の良い測定を行なうためには,一定温度で測定することが必須条件である。本装置ではガス拡散ユニット部のみならず,反応コイル及びインジェクターなどを精密に温度制御できる小型恒温槽内に収納してある。また,長期間使用に耐え得る透過効率の維持は,配管を外すことなくガス拡散セル内の滞留液を強制排除できる機能の付加により,多孔質PTFEチューブの疎水性を回復させることで可能にした。図2,3に装置内流路図と装置概略を示す。
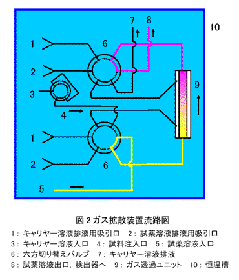
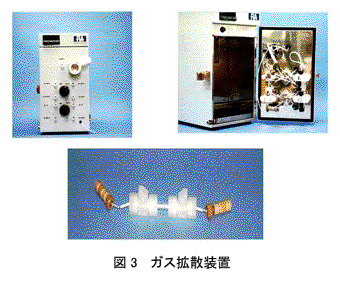
本ガス拡散装置を環境水中のアンモニア態窒素の定量に応用した。実験に用いたフローダイアグラムを図4に示す。ガス拡散装置内は40℃に保たれている。注入された試料は,反応コイルを通過する間にキャリヤー溶液中の水酸化ナトリウムと反応してアンモニウムイオンがアンモニアに変化し,多孔質PTFEチューブを通してクレゾールレッドを含む試薬溶液の流れの中に効率よく連続的に透過して吸光度変化を与える。検量線はアンモニア態窒素0〜10及び0〜1.0ppmの範囲で良好な直線性を示し(図5),2ppmの標準液を用いた10回測定における相対標準偏差は0.45%であった。1日8時間の連続運転後,1晩そのまま放置すると感度は30%低下する。これが測定終了後に溶液強制排除機能を利用することで,少なくとも2週間は感度の低下が見られず,耐久性は飛躍的に向上した。実際に河川水中のアンモニア態窒素を定量した結果を表1に示す。
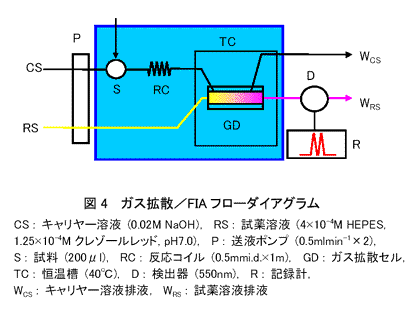
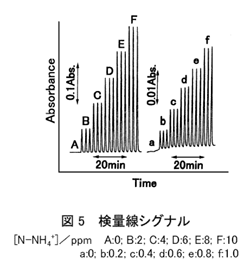
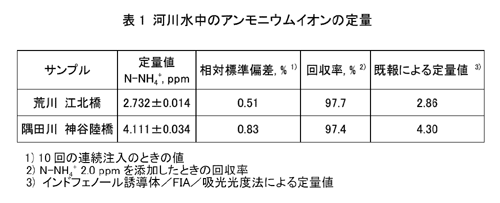
有機体窒素の定量は試料中の有機物をケルダール分解してアンモニウムイオンに変え,蒸留分離した後にインドフェノールブルー吸光光度法や中和滴定法で分析する方法が規定されている。「蒸留」は必須操作ではあるが,操作の煩雑化と分析精度の低下を招くことは言うまでもない。本研究ではケルダール法において蒸留操作を行なうことなく,直接オンラインでガス拡散前処理により定量できることを見出した。図6にフローダイアグラムを示す。分解液は最大6Nの硫酸酸性溶液の場合もあることから,水酸化ナトリウムによる気体生成反応の高効率化のために3流路系のシステムを構築した。実際の環境水試料をバッチ法によりケルダール分解し,その分解液を2分割して,蒸留/吸光光度法とガス拡散/FIA法の両者で分析を行なった結果を図7に示す。両者の間には良好な相関関係があることが分かる。
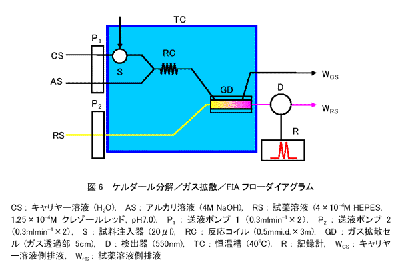
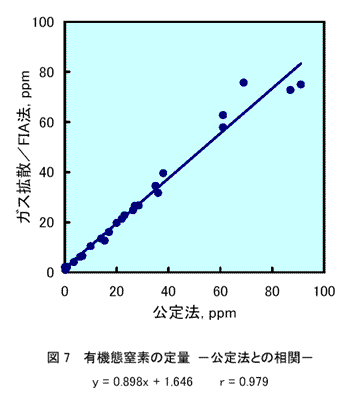
ガス拡散法は化学反応により気体となる測定対象に選択的であり,複雑なマトリックスを含む試料に極めて有効であるのみならず,蒸留に代わる前処理手段としての可能性も秘めている。本研究ではガス拡散装置としての機能を高めることで現場分析において前処理システムとしての実用化に向けて大きく前進させることができた。